「受死日(じゅしび)」は、暦の中でも特に強い凶意があるとされ、「黒日(くろび)」とも呼ばれます。結婚や引っ越し、納車など“新しい始まり”を避けたほうがよい日として知られますが、現代は日程をずらせないことも多いもの。この記事では、受死日の意味・黒日の見分け方・2026年の受死日(表は挿入枠)・避けたい行動と、気にしない場合の考え方、穏やかな過ごし方まで、実用目線で整理します。
受死日とは?黒日(くろび)とも呼ばれる「最凶日」の位置づけ
受死日(じゅしび)は、昔の暦で「下段(げだん)」と呼ばれる暦注の中に記される凶日の一つで、一般に「葬送(葬儀)以外は万事に用いない」とされてきました。現代のカレンダーでは省略されることも多いのですが、神社で授与される暦や、暦注を丁寧に載せた吉日カレンダーでは、受死日が黒い点(●)などで示されることがあり、これが「黒日(くろび)」という別名につながります。
大切なのは、受死日が「たまたま運が悪い日」というより、“始める・取り決める・区切る”行為にブレーキをかける日として扱われてきた点です。六曜(大安・仏滅など)や一粒万倍日といった他の暦注と同日に重なっても、受死日の凶意が強いとみなされ、昔は「他の暦注は見なくてよい」とまで言われたこともあります。だからこそ、結婚・入籍・引っ越し・納車・契約など、人生の節目ほど気になりやすいのです。
「黒日とは」何?受死日との違いはある?
結論から言うと、多くの暦の文脈では黒日=受死日として扱われます。黒く塗った点(●)で示すことから俗に黒日と呼ばれ、暦によっては「黒丸」「黒点」などの表現になることもあります。なお、暦の種類によっては●が“新月”など別の意味で使われる場合もあるため、「その●が受死日を指すのか」を凡例や注記で確認するのが安全です。
受死日と「十死日」など、似た凶日との混同に注意
受死日は「最凶」として語られがちですが、暦注下段には十死日・往亡日・帰忌日・血忌日など、行動を慎む系の凶日が複数あります。名称が強烈なため混同されやすいのですが、受死日は“葬送は差し支えない”とされる点が語られることが多く、十死日はそれより厳しいと説明されることもあります。
受死日はいつ?調べ方(節切りの月)と「受死日になりやすい干支」
受死日は、月ごとに特定の干支の日が当たる――という考え方で示されることが多いのですが、ここで注意したいのが「節切り(せつぎり)」です。これは、1月=1月1日〜末日という区切りではなく、立春・啓蟄など二十四節気の節目を基準に“月”を区切る見方です。暦注の計算や選日の多くは、この節切りを前提に語られます。
とはいえ、実務としては「2026年の受死日を知りたい」方がほとんどです。そこで本記事では、まず“判定ルール(目安)”を簡潔に示し、そのうえで2026年の受死日一覧吉日カレンダー表を掲載してあります。
受死日(黒日)になりやすい干支の目安(節切り)
受死日は、節切りの各月に対して、次の干支の日が当たると説明されることがあります。頻度としては、同じ十二支は約12日ごとに巡るため、ひと月に2〜3回ほど現れやすいイメージです。
| 節切りの月 | 受死日(黒日)になりやすい干支 |
|---|---|
| 正月節 | 戌の日 |
| 2月節 | 辰の日 |
| 3月節 | 亥の日 |
| 4月節 | 巳の日 |
| 5月節 | 子の日 |
| 6月節 | 午の日 |
| 7月節 | 丑の日 |
| 8月節 | 未の日 |
| 9月節 | 寅の日 |
| 10月節 | 申の日 |
| 11月節 | 卯の日 |
| 12月節 | 酉の日 |
ただし、現代のカレンダーは「節切り」ではなく「暦日(グレゴリオ暦の月)」で見ている方が多いので、混乱が起きやすいところです。
2026年の受死日カレンダー(一覧表)
2026年1月の受死日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月11日 | 先負 | 四緑木星 | 乙酉 | 成 | 房 | 神吉日 受死日 天火日 狼藉日 十方暮 |
— | 小寒 | 水泉動 | 11月23日 |
| 2026年1月23日 | 仏滅 | 七赤金星 | 丁酉 | 成 | 婁 | 神吉日 受死日 天火日 狼藉日 冬土用 天一天上 |
— | 大寒 | 款冬華 | 12月5日 |
2026年2月の受死日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月5日 | 大安 | 二黒土星 | 庚戌 | 成 | 角 | 大明日 天恩日 受死日 復日 |
— | 立春 | 東風解凍 | 12月18日 |
| 2026年2月17日 | 先勝 | 五黄土星 | 壬戌 | 成 | 室 | 八専間日 受死日 |
— | 立春 | 魚上氷 | 1月1日 |
2026年3月の受死日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月1日 | 先負 | 八白土星 | 乙亥 | 平 | 箕 | 受死日 復日 大土 |
— | 雨水 | 草木萌動 | 1月14日 |
| 2026年3月7日 | 先負 | 五黄土星 | 辛巳 | 除 | 奎 | 不成就日 天恩日 受死日 小土 |
— | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | 1月20日 |
| 2026年3月19日 | 友引 | 八白土星 | 壬辰 | 除 | 奎 | 大明日 五墓(水) 受死日 往亡日 十方暮 |
新月 | 啓蟄 | 菜虫化蝶 | 2月1日 |
| 2026年3月31日 | 友引 | 二黒土星 | 甲辰 | 除 | 星 | 大明日 月徳日 受死日 天一天上 |
— | 春分 | 雷乃発声 | 2月13日 |
2026年4月の受死日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月12日 | 先勝 | 二黒土星 | 丙辰 | 除 | 角 | 大明日 受死日 天一天上 |
— | 清明 | 鴻雁北 | 2月25日 |
| 2026年4月24日 | 仏滅 | 八白土星 | 戊辰 | 建 | 鬼 | 鬼宿日 天恩日 五墓(土) 復日 受死日 春土用 |
— | 穀雨 | 葭始生 | 3月8日 |
2026年5月の受死日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月6日 | 大安 | 五黄土星 | 庚戌 | 除 | 奎 | 受死日 小土終わり |
— | 立夏 | 蛙始鳴 | 3月20日 |
| 2026年5月18日 | 大安 | 五黄土星 | 壬辰 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日 大明日 五墓(水) 復日 受死日 十方暮 |
— | 立夏 | 竹笋生 | 4月2日 |
| 2026年5月24日 | 大安 | 二黒土星 | 戊戌 | 除 | 参 | 一粒万倍日 受死日 天一天上 |
— | 小満 | 紅花栄 | 4月8日 |
| 2026年5月30日 | 大安 | 八白土星 | 甲辰 | 閉 | 氐 | 大明日 月徳日 受死日 天一天上 |
満月 | 小満 | 麦秋至 | 4月14日 |
2026年6月の受死日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月11日 | 赤口 | 二黒土星 | 丙辰 | 閉 | 室 | 大明日 受死日 地火日 大禍日 大土 |
— | 芒種 | 腐草為蛍 | 4月26日 |
| 2026年6月23日 | 先勝 | 五黄土星 | 戊辰 | 開 | 翼 | 天恩日 五墓(土) 受死日 |
— | 夏至 | 乃東枯 | 5月9日 |
2026年7月の受死日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月5日 | 赤口 | 八白土星 | 庚戌 | 閉 | 壁 | 大明日 受死日 大禍日 小土終わり |
— | 夏至 | 半夏生 | 5月21日 |
| 2026年7月17日 | 先負 | 八白土星 | 壬辰 | 納 | 鬼 | 鬼宿日 大明日 五墓(水) 滅門日 受死日 十方暮 |
— | 小暑 | 鷹乃学習 | 6月4日 |
| 2026年7月23日 | 先負 | 五黄土星 | 戊戌 | 閉 | 翼 | 受死日 天一天上 小土 |
— | 大暑 | 桐始結花 | 6月10日 |
| 2026年7月29日 | 先負 | 二黒土星 | 甲辰 | 納 | 氐 | 大明日 月徳日 受死日 天一天上 小土 |
— | 大暑 | 土潤溽暑 | 6月16日 |
2026年8月の受死日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月7日 | 大安 | 二黒土星 | 丙辰 | 納 | 壁 | 大明日 受死日 大禍日 |
— | 立秋 | 涼風至 | 6月25日 |
| 2026年8月19日 | 先勝 | 二黒土星 | 乙丑 | 執 | 軫 | 天恩日 神吉日 五墓(木) 母倉日 受死日 帰忌日 |
— | 立秋 | 蒙霧升降 | 7月7日 |
| 2026年8月31日 | 先勝 | 二黒土星 | 丁丑 | 執 | 参 | 天恩日 月徳日 受死日 小土終わり |
— | 処暑 | 禾乃登 | 7月19日 |
2026年9月の受死日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月12日 | 先負 | 二黒土星 | 己丑 | 執 | 斗 | 天恩日 月徳日 受死日 |
— | 白露 | 鶺鴒鳴 | 8月2日 |
| 2026年9月24日 | 先負 | 二黒土星 | 辛丑 | 執 | 角 | 天恩日 月徳日 受死日 |
— | 秋分 | 雷乃収声 | 8月14日 |
2026年10月の受死日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 | 先負 | 二黒土星 | 癸丑 | 執 | 亢 | 天恩日 月徳日 受死日 |
— | 秋分 | 水始涸 | 8月26日 |
| 2026年10月18日 | 仏滅 | 五黄土星 | 乙丑 | 平 | 房 | 天恩日 神吉日 五墓(木) 十死日 地火日 滅門日 受死日 |
— | 寒露 | 蟋蟀在戸 | 9月8日 |
| 2026年10月30日 | 仏滅 | 八白土星 | 丁丑 | 平 | 斗 | 天恩日 月徳日 受死日 小土終わり |
— | 霜降 | 楓蔦黄 | 9月20日 |
2026年11月の受死日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月11日 | 友引 | 八白土星 | 己丑 | 平 | 柳 | 天恩日 月徳日 受死日 |
— | 立冬 | 地始凍 | 10月3日 |
| 2026年11月23日 | 友引 | 二黒土星 | 辛丑 | 平 | 亢 | 天恩日 月徳日 受死日 勤労感謝の日 |
— | 小雪 | 虹蔵不見 | 10月15日 |
2026年12月の受死日
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月7日 | 友引 | 八白土星 | 癸丑 | 平 | 壁 | 天恩日 月徳日 受死日 |
— | 大雪 | 閉塞成冬 | 10月29日 |
| 2026年12月19日 | 友引 | 二黒土星 | 乙丑 | 平 | 柳 | 天恩日 月徳日 受死日 |
— | 大雪 | 熊蟄穴 | — |
| 2026年12月31日 | 友引 | 五黄土星 | 丁丑 | 平 | 亢 | 天恩日 月徳日 受死日 |
— | 冬至 | 麋角解 | — |
受死日にやってはいけないこと(やめたほうが無難な行動)
受死日は「葬送以外は万事凶」と言われるほど強い凶日として扱われるため、ここでは“特に検索されやすい行動”に絞って、避けたい理由を噛み砕いて解説します。ポイントは、受死日が「失敗する」という断定より、“始める・決める・身体に手を入れる・遠くへ動く”行為に慎重さを求める日として語られてきた点です。気にするか気にしないか以前に、避けられるなら避ける、避けられないならリスクを減らす。この整理がいちばん現実的です。
1. 新しいことの開始(開店・開業・新プロジェクト・習い事のスタート)
受死日は「新しい芽」を育てる日としては相性が悪いとされます。理由はシンプルで、“始めたことが伸びにくい”と捉えられてきたからです。実際に結果がどうなるかは別として、気持ちの面で「不安の種」を抱えやすい日でもあります。スタート日を一日ずらせるなら、それだけで心が軽くなり、行動がスムーズになります。もしどうしてもこの日しか無理なら、開始を“宣言”するのではなく、準備・整理・試運転など小さく始めて大きく決めない形にしておくと、後悔が残りにくいです。
2. 結婚式・入籍・顔合わせ・婚約など慶事
受死日は、慶事との相性が悪いと語られてきました。これは「死」の字面が強いからという心理的な面もありますが、暦の考え方としては人生の節目に“凶の記号”を重ねないという発想です。周囲に年配の方がいるほど、後から「あの日は黒日だったの?」と気にするケースもあります。あなたが気にしなくても、家族や親族が気にする可能性があるなら、日取りは“調整コストが最も安い保険”になります。どうしても避けられない場合は、正式手続きは別日、当日は家族の食事会だけにするなど、節目を分散させる方法もあります。
3. 引っ越し・転居・新居の契約(受死日に動く・決める)
引っ越しは「環境を変える」「生活の土台を新しくする」行為です。受死日が気になる人ほど、転居後に小さなトラブルが起きたときに「やっぱり…」と結び付けてしまい、心の負担になりやすい面があります。暦の考え方に敬意を払うなら、契約・鍵渡し・搬入(実際に住み始める)のどれをこの日に置くかで影響度が変わる、と整理すると現実的です。日程が動かせないなら、契約の重要事項説明は別日、搬入は午前だけ・午後だけなど、工程を分けて“区切り”を弱める方法もあります。
4. 納車・車の購入・大きな契約(受死日 納車)
「受死日 納車」は特に検索が多いテーマです。納車はワクワクする反面、事故や故障など“万一”が頭をよぎりやすいイベントです。受死日を避ける人が多いのは、縁起だけでなく納車という高額イベントに不安要素を混ぜたくない心理が働くからです。避けられるなら日をずらすのが一番すっきりします。もし動かせないなら、納車そのものは受けて、正式な“お祓い・安全祈願”やドライブデビューは別日に回すなど、意味づけを分けると落ち着きやすいです。ここは気持ちの問題を軽く見ないほうが、結果的に安全運転にもつながります。
5. 買い物(受死日 買い物)…何を避けるべき?
受死日に「買い物をしてはいけない」と一括りにされることがありますが、現代の生活で“買い物ゼロ”は難しいですよね。ここは日用品の買い足しと、高額・長期使用・契約性のある買い物を分けると考えやすくなります。たとえば食品や消耗品の購入まで怖がる必要は薄い一方、財布・宝石・家電・車・不動産など、長く使うものや大きな出費は「後悔の芽」を残しやすい。受死日が気になるタイプの方ほど、後から不具合が出たときに“受死日だったから”と感じてストレスになります。避けたいのは、物そのものより後悔を育てる買い方です。買うなら比較検討は前日までに終え、当日は支払いだけ、配送日や使い始めは別日にするなど、区切りを分けると安心感が保てます。
6. 手術・鍼灸・新しい治療の開始(受死日 手術)
受死日は「この日に発病すると重くなる」など、健康面の不吉さと結び付けて語られることがあります。そのため「受死日 手術」で不安になる方も少なくありません。ただし医療は暦より優先度が高く、必要な治療を先延ばしにして体調を悪化させるほうが現実的リスクは大きいです。暦を尊重しつつ不安を軽くするなら、主治医に「日程変更が可能か」だけ相談してみて、難しければ“受死日だから不安”ではなく、術前準備・術後の生活設計・セカンドオピニオンなど、コントロールできることに意識を戻しましょう。気持ちの面では、当日を“守りを固める日”として、静かに整える過ごし方を選ぶと落ち着きます。
7. 遠方への旅行・願掛けを伴う参拝(受死日 神社参拝/受死日 参拝)
受死日は「往復の移動」や「願掛け」のような“運を動かす行為”を控えるべきと説明されることが多く、参拝もその文脈で避けられがちです。特に遠方への旅行を兼ねた参拝は、移動リスクも重なるため、気にする人ほど不安が増します。一方で、近所の神社で静かに手を合わせる程度なら「日常の延長」と考える方もいます。もし受死日が気になるなら、お願いごとを強く立てるより、感謝(お礼)と安全祈願に寄せる、長距離移動は別日にする、御朱印目的の“はしご”は避ける、といった調整で“心のざわつき”を小さくできます。
受死日に「やっていいこと」:凶日を恐れすぎないための受死日の過ごし方
受死日は「何もしてはいけない日」と捉えると苦しくなります。暦は本来、生活を縛るためではなく、季節や気持ちの整え方を示す道しるべでもあります。受死日は、派手に動くより整える・休める・確認することに向く日と考えると、現代生活に落とし込みやすいです。ここでは“無難で、実益もある過ごし方”をまとめます。
1. 普段のルーティンを丁寧に(大きく決めない)
受死日に向いているのは「いつも通り」を崩さないことです。新しい挑戦や大きな決断を避け、家事・仕事・学習など、日々の積み重ねを淡々とこなす。これだけで、凶日を意識しすぎる心の揺れが落ち着きます。暦を気にする方ほど、心の状態が行動に影響しやすいので、“いつも通り”は立派な開運行動になります。
2. 整理整頓・軽い掃除・データのバックアップ
受死日は「始める日」ではなく「整える日」にすると相性がよいと言われます。大規模な断捨離で一気に捨てるより、引き出し一段、スマホの写真整理、冷蔵庫の見直しなど、軽い範囲で。さらに現代的におすすめなのが、パスワード変更・バックアップ・契約書の整理です。凶日に備えるというより、“トラブルを未然に防ぐ整え”として実利が大きく、読者満足度も上がります。
3. 体を休める・睡眠を確保する(不安を増幅させない)
受死日に不安が強まる方は、睡眠不足や疲労で気持ちが過敏になっていることが少なくありません。早めにお風呂に入る、温かい飲み物を飲む、画面を見る時間を減らすなど、神経を鎮める方向へ。凶日を“避ける”より、“不安を増やさない体調”に寄せるほうが、結果的に運気の底上げにつながります。
4. どうしても外せない用事がある日の「現実的な守り方」
受死日を気にしない人も増えていますが、気にする・気にしないの二択ではなく、“外せない用事はやる。その代わり守りを固める”という折り合いも立派な選択です。たとえば契約なら読み合わせをいつも以上に丁寧に、納車なら保険内容の再確認、買い物なら返品条件のチェック、移動なら余裕のある行程に。暦の凶意を“恐怖”にせず、“確認と備え”に変換できると、受死日との付き合い方がぐっと楽になります。
受死日を気にしないのはアリ?(黒日 気にしない/受死日 気にしない)
「受死日を気にしないとダメですか?」という相談はとても多いです。結論から言うと、受死日は宗教上の戒律ではなく、信じ方は人それぞれです。現代では、受死日を“迷信”として扱う人もいますし、そもそもカレンダーに載っていないことも多い。だから「気にしない」選択自体が間違いということはありません。
ただし、ここで大切なのはあなたの心が納得できるかです。受死日を気にしないつもりでも、当日ずっと不安が残り、行動がぎこちなくなるなら、それはあなたにとって“気にしている”のと同じ状態です。逆に、暦を知ったうえで「私は現実の都合を優先する」と腹落ちしているなら、その選択は強い。つまり、受死日が問題なのではなく、不安の扱い方が鍵になります。
家族や職場が気にする場合の落としどころ
受死日を自分は気にしなくても、家族(特に親世代)や、職場の慣習で気にされるケースがあります。こうした場合は、相手を論破するより、“揉めない段取り”を優先するほうが運気のロスが少ないです。日程が動かせるなら動かす、動かせないなら儀式的な区切り(正式な契約日・使い始めの日・お祝いの日)だけ別日にする。暦は人間関係を整える道具として使うと、結果的に幸せに近づきます。
受死日に関するよくある質問(買い物・納車・参拝・手術)
Q1. 受死日に買い物をしてしまった…大丈夫?
日用品や生活必需品の買い物まで怖がる必要はありません。気になるのは“高額で長く使うもの”“契約性があるもの”です。もし買ってしまって不安なら、保証や返品条件を確認し、使い始めや開封を別日にするなど、あなたの心が落ち着く工夫を。暦は「不安を育てない」ことがいちばん大切です。
Q2. 受死日に納車は本当に避けるべき?
避けられるなら避ける人が多いのは事実です。ただ、避けられないなら「納車=事務手続きの日」「初乗り・お祓い=別日」と分けると安心しやすいです。安全運転と保険確認を丁寧にするほうが、運気より確実な守りになります。
Q3. 受死日に神社参拝してはいけない?
遠方参拝や願掛けを強く立てる参拝は避けたほうがよいとされがちです。一方で、近所で静かにお礼を伝える程度なら「日常の延長」と考える人もいます。不安が強いなら、参拝は別日にし、当日は家で手を合わせるだけでも十分です。
Q4. 受死日に手術や治療が入ったら?
医療は暦より優先度が高い分野です。日程変更が可能かだけ相談し、難しければ術前準備・術後ケア・情報整理など、コントロールできることに集中しましょう。凶日を怖がるより、安心材料を積むことが現実的です。
まとめ:受死日(黒日)は「避けられるなら避ける」「避けられないなら整える」
受死日(黒日)は、暦注の中でも特に凶意が強いとされ、「葬送以外は万事凶」と語られてきた日です。だからこそ、結婚・引っ越し・納車・契約・願掛けなど、人生の節目ほど不安になりやすいのも自然なこと。けれど現代は、日程を動かせない事情もあります。避けられるなら避ける。避けられないなら、確認と備えで守りを固め、心を整える。あなたが納得できる選び方を重ねていくことが、いちばんの開運につながります。

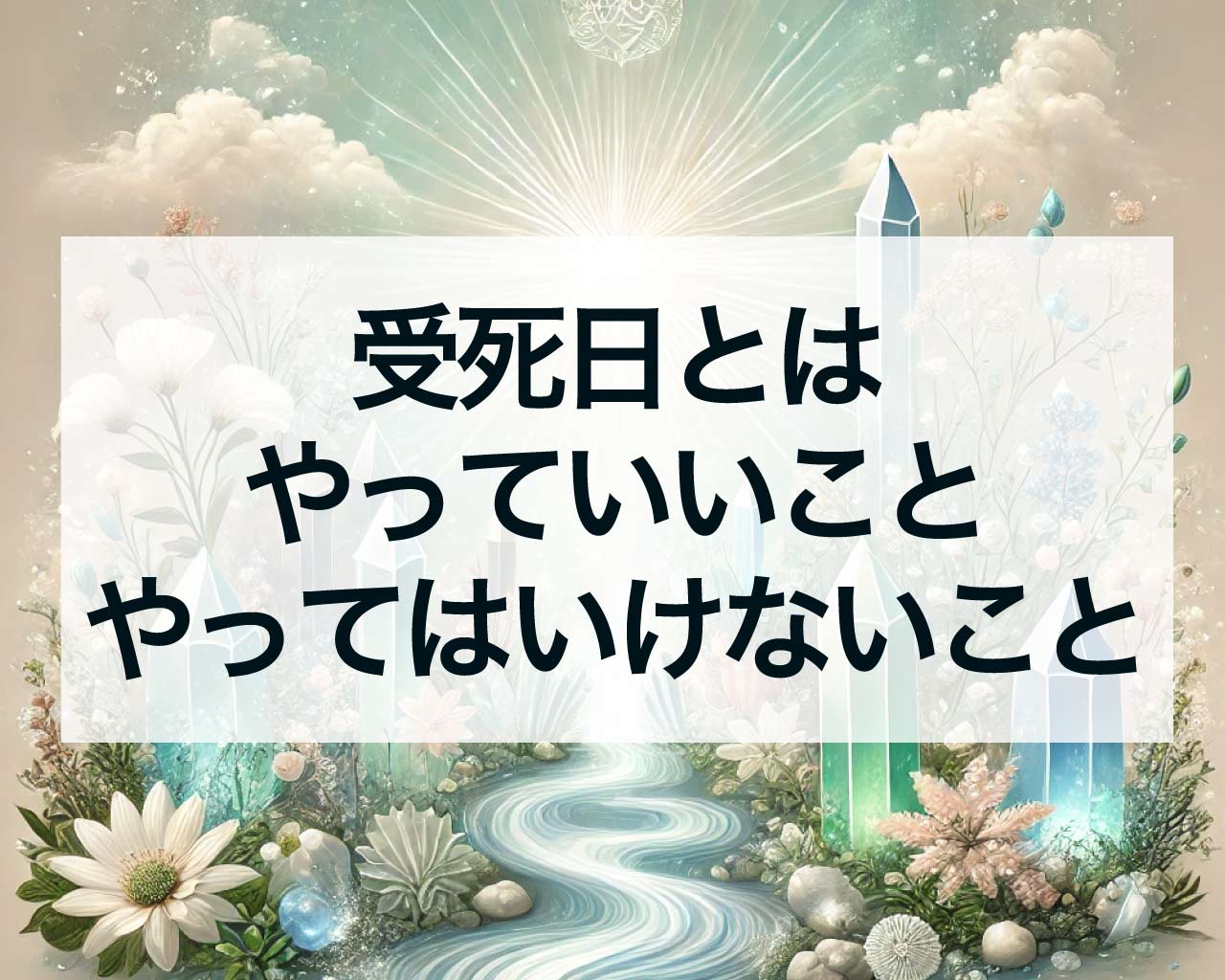
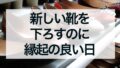
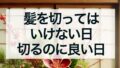

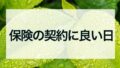

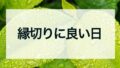
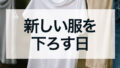
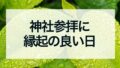
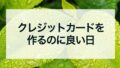
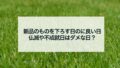

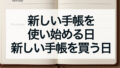
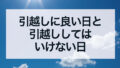










コメント