二十四節気では立夏の次は小満となります。
すっかり夏の様相になる小満…二十四節気の小満のご紹介です。
小満とは
小満(しょうまん)は、二十四節気の一つで、太陽が黄道を60度進んだ時点にあたります。一般的には5月21日頃とされ、立夏から数えて15日目頃に位置しています。この時期は、万物が成長し、生気が次第に天地に満ち始めることから小満と呼ばれています。
暦便覧の小満「万物が盈満すれば、草木枝葉が茂る」
暦便覧では小満は「万物が盈満(えいまん)すれば、草木枝葉が茂る」となっています。
自然界が活気に満ち、草木が生い茂り、枝葉が豊かになることを意味します。この言葉は、春から初夏にかけての時期に、生命力が強まり、植物が繁茂し、動物たちも活発に活動する様子を表しています。
小満の読み方は「しょうまん」
小満の読み方は「しょうまん」です。
2026年の小満は5月21日
2026年の小満は5月21日です。
小満の期間は立夏の終わりから芒種(ぼうしゅ)の前日まで
小満の期間は立夏の終わりである5月20日頃(2026年は5月21日)から芒種(ぼうしゅ)の前日である6月4日頃となります。
梅雨と小満
この小満は梅雨の時期と重なり始めます。
小満芒種(スーマンボースー)
沖縄では「小満芒種」という言葉が梅雨を意味します。
沖縄では梅雨の訪れが本州より早く、小満と芒種の間に梅雨が始まることが多いため、小満芒種が梅雨を指す言葉となりました。現在ではあまり使われなくなった言葉ですが、農作物の管理や熱中症対策の注意喚起のために、新聞で取り上げられることもあります。
走り梅雨
本州でも「走り梅雨」と呼ばれる天候が現れることがあります。これは本格的な梅雨ではないものの、沖縄の梅雨が進むことで本州の南岸にも前線が停滞し、梅雨のような天候が発生する現象です。通常はその後晴天が続いてから梅雨入りとなりますが、走り梅雨が長引いてそのまま梅雨入りする年もあるそうです。
小満は梅雨と密接な関係を持ち、作物だけでなく植物全体にとって雨が欠かせない要素です。梅雨との関連性からも、小満は植物の成長を感じるための時期となっています。
小満の七十二候
小満の七十二候のご紹介です。
蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ)
この時期は、蚕が桑の葉を積極的に食べて成長するころです。蚕は人々の生活を支える重要な存在であったため、「おかいこさま」と敬意を表して呼ばれる地域もあります。
紅花栄(べにばなさかう)
紅花が一面に咲き誇る時期です。紅花は古代エジプト時代から染料として利用されてきました。花びらから得られる水溶性の黄色色素と、水に溶けない赤色色素を組み合わせて、美しい紅色が作られます。
麦秋至(むぎのあきいたる)
麦が熟し、黄金色の穂が豊かに実る時期です。この時期は麦にとっての「秋」であり、穂が風に揺れる様子を麦嵐、また降る雨を麦雨と呼びます。
小満の食べ物
ここでは、梅雨入り前の小満の季節に楽しみたい食べ物と、それらの食材が持つ美と健康に役立つ栄養素を紹介します。これらの食材を取り入れて、季節の移り変わりを楽しみながら、健康的な生活を送りましょう。
小満に旬の食べ物、メロン
小満の時期はメロンが旬です。爽やかな風味と豊かな香りで、贅沢なデザートとして最適です。メロンにはβカロテンが豊富で、抗酸化作用があります。また、カリウムが多く含まれており、高血圧やむくみを予防し、筋肉のけいれんを防ぐ効果があります。
小満に旬の食べ物、ビワ
ビワは5~6月が食べ頃で、短い旬を楽しむフルーツです。ビワにはβカロテンが多く含まれ、髪や肌を健やかに保ちます。さらに、ポリフェノールが含まれており、細胞の老化や生活習慣病の予防に役立ちます。
小満に旬の食べ物、夏みかん
夏みかんは、初夏に爽やかな甘酸っぱさがおいしいフルーツです。夏みかん1個で1日に必要なビタミンCが摂取できます。ビタミンCは抗酸化作用があり、老化防止に役立ちます。また、ストレスに対抗する効果もあるため、肌の調子が悪い人にもおすすめです。
小満の時期の花
梅雨が近づくこの季節に美しく咲く植物を紹介します。見た目だけでなく、これらの花には美と健康にも良い効果があります。梅雨入り前のお出かけシーズンに、ぜひこれらの花々を楽しみましょう。
小満の時期の花、芍薬(しゃくやく)
芍薬は、古くから栽培された園芸植物で、美しい女性を象徴する花です。
芍薬の効能
芍薬は、薬用ハーブティーとして血行を良くする効果があります。生理不順や冷えの改善、美肌効果が期待できます。また、芍薬の香りは香水としても愛されています。
小満の時期の花、バラ
バラは5~6月に見ごろを迎え、バラ園では様々な種類のバラが咲きます。「花の女王」と称されるバラは、高貴な香りと美しい色で人々の心を惹きつけます。
バラの効能
バラの香りには、ストレスホルモンを抑える効果があり、癒し効果が期待できます。また、バラから抽出されるローズオイルには美肌効果があり、肌の潤いや弾力を取り戻し若返らせる働きがあります。
小満の季語
「小満」は、言葉自体が夏の季語として扱われ、「万物が次第に成長し、生命が満ちあふれる」季節を意味します。
小満の頃の季語は「麦秋」
小満の頃の季語として、「麦秋」や「麦の秋」が挙げられます。夏の季語でありながら「秋」という言葉が入るのは、麦の収穫時期が小満の時期であるためです。麦は冬に種を蒔き、年を越してから収穫が始まるため、「麦秋(ばくしゅう/むぎあき)」や「麦の秋」と呼ばれ、初夏の季節を象徴する言葉として親しまれています。麦の穂が黄金色に輝く光景は、稲穂が黄金色に実る秋との類似性から「秋」と表現されています。
現代の私たちが、日本を代表する作物として「米」を思い浮かべるのは自然なことかもしれません。江戸時代において、米は経済の基盤であり、その規模や扶持が米(石:こく)単位で示されることからも、米が重要な位置を占めていたことが伺えます。
しかしながら、古代から日本人の生活に重要な役割を果たしてきたのは、米だけではなく麦もまた同様でした。麦は日本人の食生活に不可欠な存在として受け入れられてきました。実際、「麦」を用いた季語が数多く存在し、日本人の生活と麦との強い結びつきを示しています。





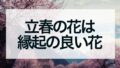

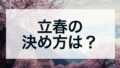
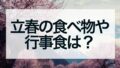
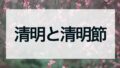



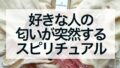

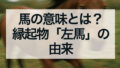
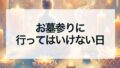

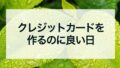
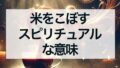
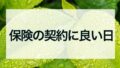
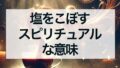


コメント