卯の日は、12日ごとに訪れるとされ、東方を象徴し、新しい始まりや希望の光を意味しています。しかし、同時にこの日には行うべきではないとされる様々な行事や活動も存在します。地域によって異なるこれらの俗信と習慣は、卯の日という特別な時間にどのような影響を及ぼしているのかご紹介します。
卯の日とは
卯の日は、干支(えと)に基づいた日の一つです。十二支の一つである「卯」が指し示す日は、12日ごとに訪れ、これを「うのひ」と読みます。卯は十二支の中で4番目に位置し、東の方角を意味します。また、「卯の刻」と呼ばれる時間帯は、朝の5時から7時までを指し、新しい一日の始まりと関連付けられています。
干支と十二支の歴史
十二支は、紀元前の中国で始まった暦法で、時間や年を区切るためのシステムとして用いられてきました。それぞれの支は、子(ね)、丑(うし)、寅(とら)、卯(う)、辰(たつ)、巳(み)、午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)、亥(い)といった動物によって象徴されています。これらは、木星の約12年の公転周期にちなんで天を12等分したものであり、古代中国では木星の位置に基づいて年を数える方法として重要な役割を果たしていました。
さらに、これらの十二支はもともと漢字で表されていましたが、後に王充という人物によって動物の名前に変更され、現在知られる干支の形になりました。これは、人々にとってより身近で理解しやすいものとなり、日常生活に深く根ざしていくきっかけとなりました。
卯の日には子宝祈願
子宝祈願、子孫繁栄を願う際、特に吉とされる日があります。それが「子の日(ねのひ)」と「卯の日(うのひ)」です。これらの日は、干支の一つである「子(ねずみ)」と「卯(うさぎ)」に当たる日で、それぞれ子沢山としての象徴とされています。ねずみとうさぎは、その繁殖力の高さから、多くの子孫をもたらす象徴として古くから信仰されています。子宝祈願は、干支だけではなく大安や仏滅といった六曜を気にされる方も多いですよ〜。
子の日と卯の日は、特に子授けや子孫繁栄を願う方々にとって重要な日とされており、多くの夫婦がこれらの日に合わせて神社での祈願や特別な儀式を行います。しかし、もちろん、これらの日に限らず、ご自身の都合の良い日で祈願を行うことも可能です。大切なのは、心からの願いを込めることです。
卯の日にすること
それでは卯の日にすること、するといいことのご紹介です。
卯の日にすること、初卯詣
「初卯詣」という言葉を聞いたことがない人も多いと思います。
これは「はつうもうで」と読み、「初詣(はつもうで)」とはちょっと違います。
「初詣(はつもうで)」は、「その年最初に参詣すること」ですが、「初卯詣(はつうもうで)」は「新年最初の『卯(う)』の日に参詣すること」を言います。
うさぎを神獣としてまつっている神社は全国にいくつかあります。うさぎの繁殖力の強さにあやかって、子宝祈願や安産祈願で人気ですよ〜。
初卯についてはこちらの記事を読んでくださいね!
卯の日にすること、七五三や百日などの慶事
卯の日重ねという言葉があります。これは卯の日に吉事を行うと良いことが重なるという意味で、七五三や百日といった慶事をお祝いすると良いことが重なると言われています。
ただし、良いことでも結婚式は二度あってはいけないので避けます。
卯の日にやってはいけないこと
卯の日は干支に基づく特別な日であり、その日に行うべきではないとされる様々な俗信が存在します。地域によってその内容は異なりますが、ここでは一般的に知られているものを紹介します。ただし、これらはあくまで伝統的な信仰や地域の風習に基づいたものなので、知らなかったという方は興味本位で捉えてみてください。
卯の日に結婚式と葬式はやってはいけない
“卯の日重ね”という言葉がありますが、「うのひがさね」と読み、これは卯の日に吉事を行うと良いことが重なるとされる一方で、凶事はさらに悪化するという信仰です。特に、葬儀や墓参りなどは避けられることが多く、結婚式も再婚を意味するため避けるとされています。
卯の日に田植えはやってはいけない
多くの地域で、卯の日に田植えをすることは避けられています。その理由は様々ですが、代表的なものには以下のようなものがあります。
- 卯の日は田の神様が休む日とされ、人も休むべきという考え。
- 卯の日に田植えをするとその年に家族の中でお米を食べられない人が出るという信仰。これは病気や死を連想させるものです。
- 一家の大黒柱が亡くなるという不吉な予兆とされること。
卯の日に餅つきはやってはいけない
餅つきも卯の日は避けるべき行事とされています。卯の日に餅をつくと神隠しに遭うという俗説があるためです。
卯の日と坎日(かんにち)
卯の日の避けるべき行事は、坎日という陰陽道での忌み日から来ている可能性があります。坎日は、凶とされる日で、この日に外出や種まきを避ける風習がありました。特に5月の卯の日は坎日に当たることが多く、そのため田植えを避けたのかもしれません。
地域差と個人の判断
これらの俗信は非常に地域色が強く、お住まいの場所やご家族の伝統によって異なる場合が多いです。全く聞いたことがない、という方も少なくありません。古い風習として興味深く捉えるもよし、実際に避けるもよし、ご自身で情報を確かめ、どのように取り入れるかを決めることが大切です。
2025年の卯の日
2025年の「卯の日」をまとめた表です。
| 干支 | 日付 | 曜日 | 六曜 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|
| 己卯(つちのとう) | 1月10日 | 金曜日 | 仏滅 | 2024年12月11日 |
| 辛卯(かのとう) | 1月22日 | 水曜日 | 仏滅 | 2024年12月23日 |
| 癸卯(みずのとう) | 2月3日 | 月曜日 | 赤口 | 2025年1月6日 |
| 乙卯(きのとう) | 2月15日 | 土曜日 | 赤口 | 2025年1月18日 |
| 丁卯(ひのとう) | 2月27日 | 木曜日 | 赤口 | 2025年1月30日 |
| 己卯(つちのとう) | 3月11日 | 火曜日 | 先勝 | 2025年2月12日 |
| 辛卯(かのとう) | 3月23日 | 日曜日 | 先勝 | 2025年2月24日 |
| 癸卯(みずのとう) | 4月4日 | 金曜日 | 先負 | 2025年3月7日 |
| 乙卯(きのとう) | 4月16日 | 水曜日 | 先負 | 2025年3月19日 |
| 丁卯(ひのとう) | 4月28日 | 月曜日 | 仏滅 | 2025年4月1日 |
| 己卯(つちのとう) | 5月10日 | 土曜日 | 仏滅 | 2025年4月13日 |
| 辛卯(かのとう) | 5月22日 | 木曜日 | 仏滅 | 2025年4月25日 |
| 癸卯(みずのとう) | 6月3日 | 火曜日 | 赤口 | 2025年5月8日 |
| 乙卯(きのとう) | 6月15日 | 日曜日 | 赤口 | 2025年5月20日 |
| 丁卯(ひのとう) | 6月27日 | 金曜日 | 友引 | 2025年6月3日 |
| 己卯(つちのとう) | 7月9日 | 水曜日 | 友引 | 2025年6月15日 |
| 辛卯(かのとう) | 7月21日 | 月曜日 | 友引 | 2025年6月27日 |
| 癸卯(みずのとう) | 8月2日 | 土曜日 | 友引 | 2025年6月9日 |
| 乙卯(きのとう) | 8月14日 | 木曜日 | 友引 | 2025年6月21日 |
| 丁卯(ひのとう) | 8月26日 | 火曜日 | 仏滅 | 2025年7月4日 |
| 己卯(つちのとう) | 9月7日 | 日曜日 | 仏滅 | 2025年7月16日 |
| 辛卯(かのとう) | 9月19日 | 金曜日 | 仏滅 | 2025年7月28日 |
| 癸卯(みずのとう) | 10月1日 | 水曜日 | 大安 | 2025年8月10日 |
| 乙卯(きのとう) | 10月13日 | 月曜日 | 大安 | 2025年8月22日 |
| 丁卯(ひのとう) | 10月25日 | 土曜日 | 先勝 | 2025年9月5日 |
| 己卯(つちのとう) | 11月6日 | 木曜日 | 先勝 | 2025年9月17日 |
| 辛卯(かのとう) | 11月18日 | 火曜日 | 先勝 | 2025年9月29日 |
| 癸卯(みずのとう) | 11月30日 | 日曜日 | 友引 | 2025年10月11日 |
| 乙卯(きのとう) | 12月12日 | 金曜日 | 友引 | 2025年10月23日 |
| 丁卯(ひのとう) | 12月24日 | 水曜日 | 先負 | 2025年11月5日 |
2026年の卯の日
2026年の「卯の日」をまとめた表です。
| 日付 | 六曜 | 九星 | 干支 | 十二直 | 二十八宿 | 暦注下段 | 新月満月 | 二十四節気 | 七十二候 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月05日(月) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 満 | 張 | 小寒/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日/復日 | 小寒 | 芹乃栄 | 11月17日 | |
| 2026年01月17日(土) | 先負 | 一白水星 | 辛卯 | 満 | 女 | 一粒万倍日/不成就日/土用入り/神吉日 | 11月29日 | |||
| 2026年01月29日(木) | 仏滅 | 四緑木星 | 癸卯 | 満 | 井 | 一粒万倍日/神吉日 | 12月11日 | |||
| 2026年02月10日(火) | 仏滅 | 七赤金星 | 乙卯 | 除 | 尾 | 神吉日/往亡日 | 12月23日 | |||
| 2026年02月22日(日) | 赤口 | 一白水星 | 丁卯 | 除 | 昴 | 天恩日/神吉日 | 1月6日 | |||
| 2026年03月06日(金) | 赤口 | 四緑木星 | 己卯 | 建 | 亢 | 大明日/天恩日/神吉日/天火日/狼藉日 | 1月18日 | |||
| 2026年03月18日(水) | 赤口 | 七赤金星 | 辛卯 | 建 | 壁 | 神吉日/復日/天火日/狼藉日 | 1月30日 | |||
| 2026年03月30日(月) | 先勝 | 一白水星 | 癸卯 | 建 | 張 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 2月12日 | |||
| 2026年04月11日(土) | 先勝 | 四緑木星 | 乙卯 | 閉 | 女 | 一粒万倍日/神吉日 | 2月24日 | |||
| 2026年04月23日(木) | 先負 | 七赤金星 | 丁卯 | 閉 | 井 | 一粒万倍日/天恩日/神吉日 | 3月7日 | |||
| 2026年05月05日(火)
祝日/こどもの日 |
先負 | 一白水星 | 己卯 | 閉 | 尾 | 立夏/一粒万倍日/大明日/天恩日/神吉日 | 立夏 | 蛙始鳴 | 3月19日 | |
| 2026年05月17日(日) | 仏滅 | 四緑木星 | 辛卯 | 開 | 昴 | 一粒万倍日/神吉日/母倉日 | 新月 | 4月1日 | ||
| 2026年05月29日(金) | 仏滅 | 七赤金星 | 癸卯 | 開 | 亢 | 一粒万倍日/神吉日/母倉日 | 4月13日 | |||
| 2026年06月10日(水) | 仏滅 | 一白水星 | 乙卯 | 納 | 壁 | 神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | 4月25日 | |||
| 2026年06月22日(月) | 赤口 | 六白金星 | 丁卯 | 納 | 張 | 天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/復日/大禍日 | 5月8日 | |||
| 2026年07月04日(土) | 赤口 | 三碧木星 | 己卯 | 納 | 女 | 大明日/天恩日/神吉日/母倉日/血忌日/大禍日 | 5月20日 | |||
| 2026年07月16日(木) | 友引 | 九紫火星 | 辛卯 | 成 | 井 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 6月3日 | |||
| 2026年07月28日(火) | 友引 | 六白金星 | 癸卯 | 成 | 尾 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 土潤溽暑 | 6月15日 | ||
| 2026年08月09日(日) | 友引 | 三碧木星 | 乙卯 | 危 | 昴 | 神吉日 | 6月27日 | |||
| 2026年08月21日(金) | 先負 | 九紫火星 | 丁卯 | 危 | 亢 | 天恩日/神吉日 | 7月9日 | |||
| 2026年09月02日(水) | 先負 | 六白金星 | 己卯 | 危 | 壁 | 大明日/天恩日/神吉日 | 禾乃登 | 7月21日 | ||
| 2026年09月14日(月) | 大安 | 三碧木星 | 辛卯 | 破 | 張 | 一粒万倍日/神吉日/復日 | 8月4日 | |||
| 2026年09月26日(土) | 大安 | 九紫火星 | 癸卯 | 破 | 女 | 一粒万倍日/神吉日 | 8月16日 | |||
| 2026年10月08日(木) | 大安 | 六白金星 | 乙卯 | 執 | 井 | 寒露/神吉日 | 寒露 | 鴻雁来 | 8月28日 | |
| 2026年10月20日(火) | 赤口 | 三碧木星 | 丁卯 | 執 | 尾 | 土用入り/天恩日/神吉日 | 9月10日 | |||
| 2026年11月01日(日) | 赤口 | 九紫火星 | 己卯 | 執 | 昴 | 大明日/天恩日/神吉日/復日 | 9月22日 | |||
| 2026年11月13日(金) | 友引 | 六白金星 | 辛卯 | 定 | 亢 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 10月5日 | |||
| 2026年11月25日(水) | 友引 | 三碧木星 | 癸卯 | 定 | 壁 | 神吉日/天火日/狼藉日 | 10月17日 | |||
| 2026年12月07日(月) | 友引 | 九紫火星 | 乙卯 | 平 | 張 | 大雪/神吉日/受死日/地火日/滅門日 | 大雪 | 閉塞成冬 | 10月29日 | |
| 2026年12月19日(土) | 先負 | 四緑木星 | 丁卯 | 平 | 女 | 天恩日/神吉日/受死日/復日/地火日/滅門日 | 11月11日 | |||
| 2026年12月31日(木) | 先負 | 七赤金星 | 己卯 | 平 | 井 | 大明日/天恩日/神吉日/受死日/地火日/滅門日 | 11月23日 |
うさぎ年・卯年一覧と卯年生まれの年齢早見表
記は年齢早見表でうさぎ年・卯年生まれの人の年齢を一目で分かります。
2024年時点の年齢となっています。次の卯年は2034年辛卯 (かのとう)となっています。
| 生まれ年(和暦) | 満年齢 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2023年生まれ (令和5年) |
1歳 | 卯(うさぎ) | 癸卯 (みずのとう) |
| 2011年生まれ (平成23年) |
13歳 | 卯(うさぎ) | 辛卯 (かのとう) |
| 1999年生まれ (平成11年) |
25歳 | 卯(うさぎ) | 己卯 (つちのとう) |
| 1987年生まれ (昭和62年) |
37歳 | 卯(うさぎ) | 丁卯 (ひのとう) |
| 1975年生まれ (昭和50年) |
49歳 | 卯(うさぎ) | 乙卯 (きのとう) |
| 1963年生まれ (昭和38年) |
61歳 | 卯(うさぎ) | 癸卯 (みずのとう) |
| 1951年生まれ (昭和26年) |
73歳 | 卯(うさぎ) | 辛卯 (かのとう) |
| 1939年生まれ (昭和14年) |
85歳 | 卯(うさぎ) | 己卯 (つちのとう) |
| 1927年生まれ (昭和2年) |
97歳 | 卯(うさぎ) | 丁卯 (ひのとう) |
| 1915年生まれ (大正4年) |
109歳 | 卯(うさぎ) | 乙卯 (きのとう) |
| 1903年生まれ (明治36年) |
121歳 | 卯(うさぎ) | 癸卯 (みずのとう) |
| 1891年生まれ (明治24年) |
133歳 | 卯(うさぎ) | 辛卯 (かのとう) |
| 1871年生まれ (明治12年) |
145歳 | 卯(うさぎ) | 己卯 (つちのとう) |
卯年生まれの有名人
- 永野芽郁 1999年生まれ
- 長澤まさみ 1987年生まれ
- 米倉涼子 1975年生まれ
- 松重豊 1963年生まれ
- 小林薫 1951年生まれ


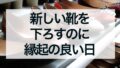
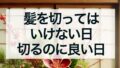
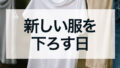


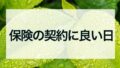

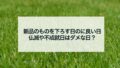
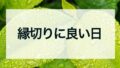



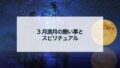
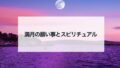
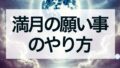
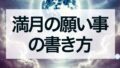
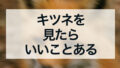
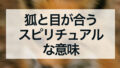
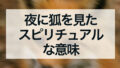
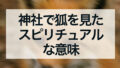


コメント