一年で最も寒さが厳しいとされる時期、「小寒」について探ります。小寒は、寒さが少しずつ増していく時期であり、この時期を「寒の入り」と呼びます。また、この厳しい寒さを利用した伝統的な食品製造法である「寒仕込み」にも焦点を当てます。日本の伝統文化に根ざしたこれらの概念を通じて、冬の寒さがもたらす恵みと、それを最大限に活かす知恵と技について、詳しく見ていきます。小寒の時期の深い意味と、寒仕込みがもたらす豊かな味わいを一緒に探求しましょう。
小寒とは
小寒(しょうかん)は二十四節気の一つで、寒さが次第に強まる時期を示します。この名前は、寒さがまだ「小さい」という意味から来ており、一年で最も寒い「大寒」に向けて寒さが徐々に厳しくなることを表します。通常、陰暦の冬から立春までの約30日間を指し、この期間は一年で最も寒いとされています。この時期は前半の15日間を小寒、後半の15日間を大寒と分けて考えます。小寒の最初の日は「寒の入り」と呼ばれ、小寒から大寒にかけての約30日間(1月6日頃から2月3日頃まで)は「寒」や「寒中」、「寒の内」と称され、一年中で最も寒さが厳しい時期とされています。小寒は毎年1月5日から1月19日までの期間に設定されています。
2026年の小寒
2026年1月5日が小寒となります。
寒の入りとは
二十四節気の一つである「小寒」は、寒さが徐々に厳しくなっていく時期を示し、「寒の入り」とも呼ばれます。この期間は、中国で農作業の目安として作られた季節を示す基準の一部として、古くから親しまれてきました。小寒から立春前日の節分までを「寒」または「寒の内」と称し、この約1か月間は、日本において特別な意味を持つ時期です。
寒の入りとは?
寒の入りは、1年の中で寒さが本格化するサインとされています。この時期は、冬至を過ぎ、日が少しずつ長くなり始めるものの、気温は下がり続け、自然界では最も厳しい寒さが訪れます。この小寒から大寒にかけての期間は、寒さが最も厳しいとされ、「大寒」が1年中で最も寒い時期を表します。
寒の内と寒明け
「寒の内」とは、小寒から節分までの約1か月間を指します。この時期は、自然が休息し、人々が内省するには絶好の時期とされてきました。そして、寒の内が終わり、立春を迎えることを「寒明け」といいます。寒明けは、冬の寒さが和らぎ、春の訪れを感じる瞬間として、多くの人々にとって特別な意味を持ちます。
寒稽古: 寒の内の鍛錬
「寒稽古」とは、寒の期間に特に行われる武道や音楽などの鍛錬です。厳しい寒さの中でも練習を怠らず、自己を高めることによって、精神的な強さや技術の向上を目指します。寒稽古は、ただ単に技能を磨くだけでなく、寒さを乗り越えることで心身を鍛える重要な行事とされています。
小寒から始まる「寒の入り」は、年間を通じて最も寒さが厳しい時期を迎えるとともに、内省と鍛錬の機会を提供します。この時期に行われる寒稽古や、寒の内を乗り越えて迎える寒明けは、春の訪れをより一層楽しみにさせる文化的な要素として大切にされています。冬の寒さを深く理解し、その中で見出される美しさや意義を味わうことで、季節の変化をより豊かに感じることができるでしょう。
小寒と寒仕込み
二十四節気の一つ「小寒」は、一年で最も気温が低くなる時期の幕開けです。この時期は、発酵食品の仕込みにとって理想的な環境を提供し、日本の伝統食品の製造に欠かせないタイミングとされています。自然の寒さを活用した「寒仕込み」や「寒造り」は、日本酒、味噌など多くの発酵食品の製造過程で重要な役割を果たしています。
寒造りの歴史と現代
かつて、自然の変化に合わせて発酵をコントロールしていた時代には、寒の時期に製造される「寒酒」が高品質とされていました。江戸時代には伊丹の蔵元がこの製法を発展させ、後に幕府の指導で冬季限定の醸造が定められました。これにより、冬に仕事が少ない農家や漁師が酒蔵で働くようになり、専門家「杜氏」としてお酒造りに携わるようになります。今日では、技術の進化により一年中安定した発酵環境が整えられていますが、伝統的な寒造りは冬季限定で活躍する杜氏によって今もなお守られています。
自宅で楽しむ寒仕込み
寒仕込みは、発酵ビギナーにもおすすめの活動です。暑い時期よりも雑菌が入りにくく、発酵スピードが緩やかなため、失敗しにくいのが特徴です。本格的なお味噌や一夜漬けなど、様々な発酵食品を手作りしてみましょう。また、寒の時期は漬ける速度が遅いため、漬かり具合をゆっくりと楽しむことができます。
手作りの楽しみを広げよう
お漬物だけでなく、フルーツ酢の作成もおすすめです。いちごやりんごなどの冬の果物を使って、自家製のフルーツ酢に挑戦してみましょう。基本的な比率は果物、酢、砂糖を1:1:1で、冬は発酵がゆっくり進むため、過発酵の心配が少なく、じっくりと待つことで美味しいフルーツ酢が完成します。
寒い時期だからこそ楽しめる「寒仕込み」。伝統的な日本酒や味噌から、家庭でも簡単に挑戦できる一夜漬けやフルーツ酢まで、幅広い発酵食品を作る楽しみをこの小寒の期間に探求してみませんか?自然の寒さを活かした発酵のプロセスは、あなたにとって新たな発見と美味しい成果をもたらすことでしょう。冬の寒さを活かして、美味しい発酵食品の仕込みを楽しんでみてください。



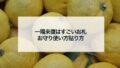
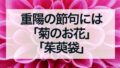
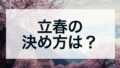
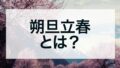
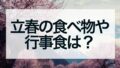
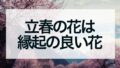




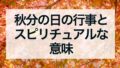
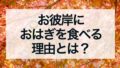
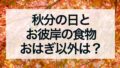
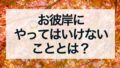

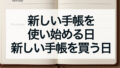
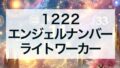
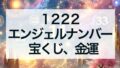


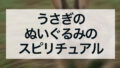
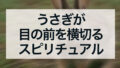

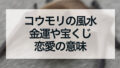


コメント