立冬の季節がやってくると、秋の終わりと冬の始まりが交差するこの特別な時期を迎えます。日本の伝統的な暦の中で、立冬は「冬の入り口」とされ、冬への準備と心の中での移行を感じる時期です。この時期には、様々な行事が行われ、また日常の中での過ごし方も少しずつ変わってきます。それでは、立冬の時期に行われる行事や、この季節を心地よく過ごすための方法について、詳しくご紹介していきましょう。
立冬とは、冬の訪れを告げる季節の節目
立冬とは、二十四節気の中のひとつで、冬の始まりを意味します。言葉の通り、この時期は冬が立ち上がる、すなわち冬の到来を告げるものとして位置付けられています。
『暦便覧』によれば、「冬の気立ち初めて、いよいよ冷ゆれば也」と述べられています。これは冬の気配が本格的に感じられ始めるこの時期の様子を表しています。立冬の期間は新暦で11月7日から11月21日頃までとされています。
実際の天気や気温を感じてみると、まだ真の冬とは言えないのかもしれません。しかし、この時期になると日差しの強さが少し和らぎ、一部の地域では初冠雪の便りが届くこともあります。また、木枯らしと名付けられた冷たい風が吹き始め、木々が落ち葉の絨毯となり、徐々に冬の風景へと移り変わっていきます。
立冬を迎える前に、冬支度を始めるのが良いでしょう。急な気温の変動に対応するためにも、冬の準備を少しずつ始めることで、心地よく季節の変わり目を迎えることができます。
この立冬の時期に、冬の訪れを感じながら、四季折々の日本の自然や風物詩を楽しみましょう。
立冬の行事とやること、七五三と亥の子餅
立冬は、冬の訪れを感じさせる季節の節目として、日本全国でさまざまな行事が行われます。その中でも、特に目立つ行事として「七五三」と「亥の子餅」があります。これらの行事は、日本の文化や歴史の中で子どもたちの健康や家族の繁栄を祈願する意味が込められています。
立冬の行事、七五三:子どもの成長と健康を願う神事
七五三は、子どもの成長をお祝いし、その健康と幸福を祈るための行事です。具体的には、男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳の際に、家族と共に神社へと参拝します。この歳は、昔から子どもの成長の重要な節目とされており、無事にこの年齢を迎えられたことの感謝と、今後のさらなる成長を願う意味が込められています。
立冬の時期と重なる11月15日頃には、子供たちの健やかな成長と将来を願う「七五三」の行事が行われます。
子供たちには、願いや意味を込めて特別な儀式が施されます。3歳の子供たちは「髪置きの儀」として髪を伸ばし始め、5歳の男の子は「袴儀」として初めて袴を着ることとなります。7歳の女の子は「帯び解きの儀」として、大人と同じように帯を結ぶようになります。この日には、長寿を願い、千歳飴という特別な飴を子供たちに与えられます。
木枯らし一号:冬の足跡を感じる風
立冬の季節に吹く「木枯らし」は、冬の到来を感じさせる象徴的な風です。冷たく強い北風であり、これが吹き始めると、本格的な冬の気配を感じるようになります。特に「木枯らし一号」として発表される時期は、多くの地域で落葉樹の葉が一気に散り、冬の風景へと変わります。
立冬の行事、亥の子餅:繁栄と健康を祈る伝統の行事
亥の子餅は、主に関西地方で行われる行事で、イノシシの子を模った餅を作る習慣があります。イノシシは多産であることから、この行事は子孫繁栄や家族の健康を祈願する意味が込められています。また、収穫の喜びや無病息災を祈る意味合いも持ち合わせています。
これらの行事は、立冬の季節に行われることで、新しい季節の中での家族の絆や子どもたちの未来を祈る、日本人ならではの温かい気持ちを感じさせてくれます。立冬を迎えるこの時期に、是非これらの行事を体験して、日本の伝統や文化を感じてみてください。
お茶は立冬が新年
多くの日本人にとって新しい年の始まりは、1月1日のお正月ですが、茶の湯の深い伝統の中には独自のカレンダーが存在します。そこでは、立冬が新たな年の幕開けと捉えられています。
立冬を新しい年のスタートとするこの風習は、春に収穫した新茶の扱いに由来します。この新しい茶葉は、立冬まで茶つぼに保管され、立冬の日に特別な儀式「口切」として開封されます。この儀式は、新たな一年の茶の湯の始まりを祝福する大切な瞬間として広く認識されています。
さらに、この特別な日には、茶室や庭を新たに整える習慣も存在します。立冬の正午には「炉開き」と呼ばれる茶事が行われ、これが最も格式のある茶の湯の行事とされています。炉の火が新たに灯されるこの時期は、心新たに茶の湯を楽しむ一年の始まりとして、多くの茶人たちに大切にされています。
総じて、立冬は茶の湯の世界において、新しい年の始まりを祝福し、再出発の気持ちを新たにする大切な時期です。この時期を迎えることで、日常生活においても新しい気持ちで一年を迎えることができるでしょう。
立冬の候はいつ使う?季節を感じる日本の伝統的なあいさつ
日本には四季の移り変わりを感じさせる独特の挨拶、時候の挨拶が存在します。その中でも、11月7日から21日頃にかけての「立冬」の時期に使う「立冬の候」は、手紙の冒頭にぴったりの表現です。
この時期に手紙や葉書を書く際には、「拝啓、立冬の候、お身体に何らかの変わりはございませんか」といった具体的な挨拶で、季節感を添えることができます。受け取った側も季節の変わり目を感じることができ、より一層の温かみを感じることができるでしょう。
また、「立冬の折柄」や「立冬の節分に」といった表現も利用できます。これらの表現は、古き良き日本の伝統を感じさせ、文面全体に深みをもたらします。
立冬の時期は、自然の中で感じる変化を文章の中でも感じ取ることができる素晴らしい時期です。手紙や葉書の書き始めに、この「立冬の候」を取り入れて、季節の美しさを共有してみませんか?

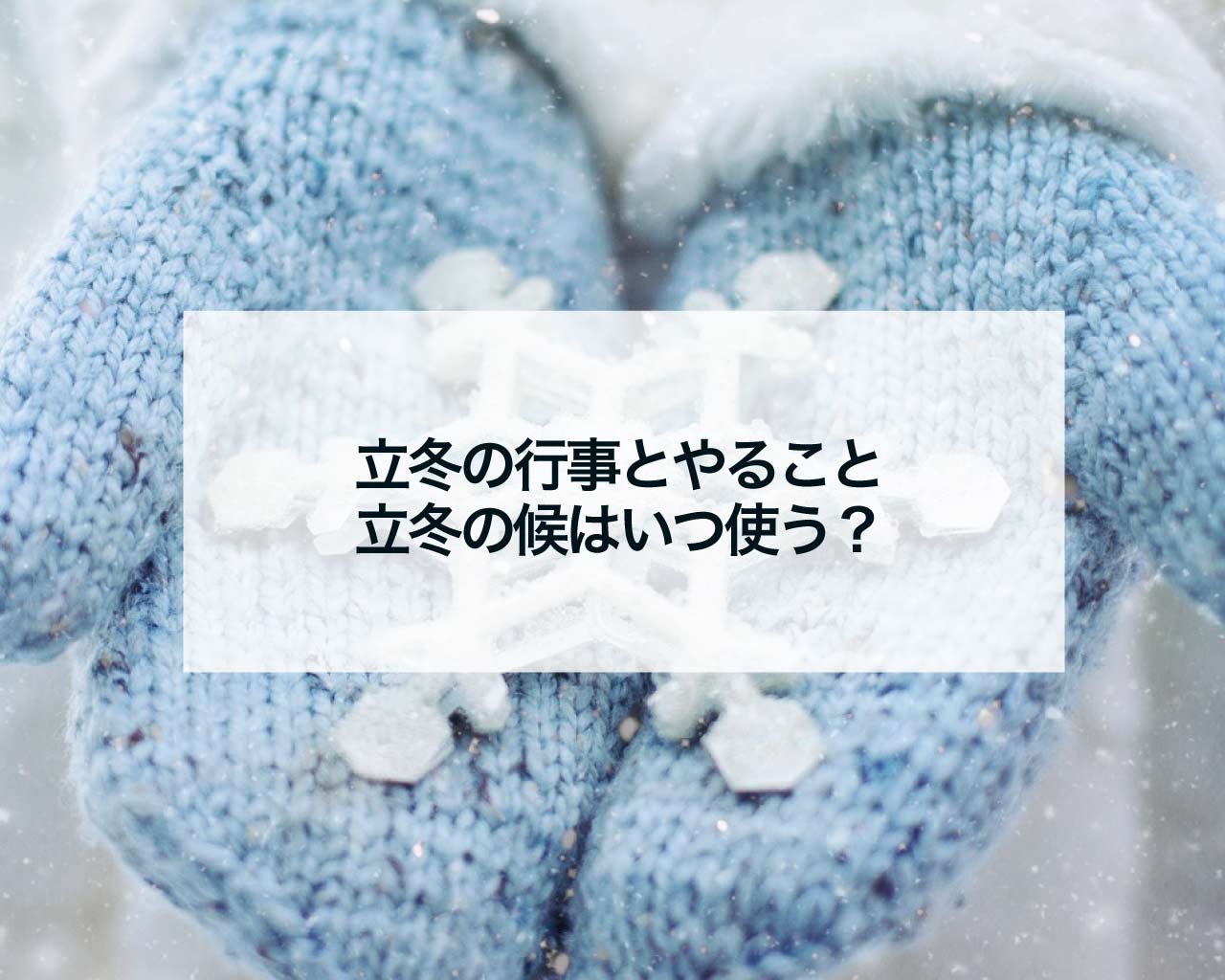
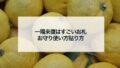
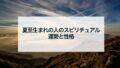


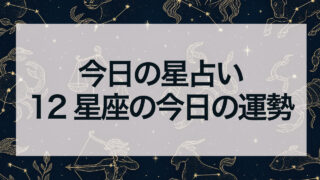

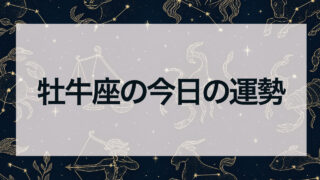
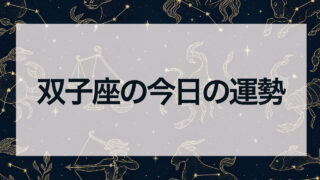
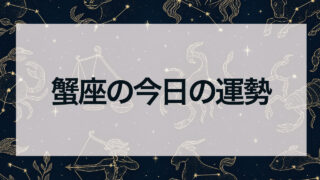
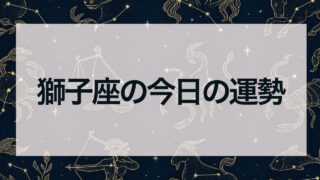
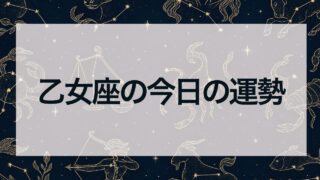
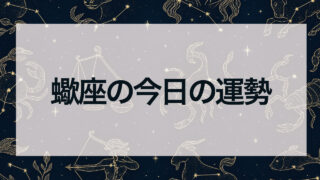


コメント