啓蟄は春の訪れを告げる二十四節気の一つです。この時期には、冬眠していた生き物たちが土の中から這い出てくる様子が見られ、一年で最も生命力に満ち溢れる瞬間を迎えます。啓蟄の由来は、まさにこの自然現象に基づいており、「啓」が「開ける」という意味を、「蟄」が冬眠中の虫を指すことから、「冬ごもりしていた虫が土を破って出てくる」という意味合いを持つのです。この時期は、気候も穏やかになり始め、生きとし生けるものが新たな季節を迎える準備を始める象徴的な節目となります。
啓蟄とは、由来と意味
啓蟄は、季節の変わり目をより詳細に分類した「二十四節気」の一つで、春が始まる直前、大体3月の初旬から中旬にかけての期間を示します。この時期は、冬の間に休眠していた生物が目を覚ます特別な時です。
啓蟄は太陽黄径345度の位置に来た日と定義されており、例年3月6日頃です。節気では3番目となります。
啓蟄の由来と意味
言葉の意味に着目すると、「啓」は「開く」や「開放する」を、「蟄」は冬眠中の虫が土の中に潜り、外界から隔てられている状態を表します。これらは、春を迎える準備として、地中から生き物たちが姿を現す様子を象徴しています。
啓蟄の期間は、自然界における新たな始まりを告げ、動植物にとって重要な転換点となります。この時期には、様々な生き物が活動を再開し、自然が再び生き生きとした動きを見せ始めるのです。
二十四節気とは
二十四節気は、太陽の位置と地球上の太陽光の量に基づいて定められた伝統的な暦の体系です。このシステムでは、1年を四季に区分し、さらに各季節を6つの段階に細分化して、合計24の時期に分けています。これらにはそれぞれ独自の名称が付けられ、季節の変化や自然のリズムを象徴しています。
啓蟄を含む二十四節気には、立春や春分、夏至、大暑、立秋などがあり、それぞれが特定の季節の始まりや中点を示します。年によって日付はわずかに異なり、通常1日程度の前後が見られます。
啓蟄の期間2026
啓蟄は毎年3月の初旬から中旬にかけての期間を指し、具体的には3月5日から3月19日頃とされます。この期間は年によって微妙に変わるため、啓蟄が指すのは「啓蟄に入る日」だけでなく、春分に至るまでの一定期間を含むこともあります。
| 2024年の啓蟄 | 2024年3月5日(火曜日) |
| 2025年の啓蟄 | 2025年3月5日(水曜日) |
| 2026年の啓蟄 | 2026年3月5日(木曜日) |
| 2027年の啓蟄 | 2027年3月6日(土曜日) |
| 2028年の啓蟄 | 2028年3月5日(日曜日) |
| 2029年の啓蟄 | 2029年3月5日(月曜日) |
| 2030年の啓蟄 | 2030年3月5日(火曜日) |
啓蟄の初候と次候と末候
啓蟄の時期の初候と次候と末候は下記になります。
| 初候 | 3月5日〜9日 | すごもりむしとをひらく | 蟄虫啓戸 | 冬籠りの虫が出て来る |
| 次候 | 3月10日〜14日 | ももはじめてさく | 桃始笑 | 桃の花が咲き始める |
| 末候 | 3月15日〜19日 | なむしちょうとなる | 菜虫化蝶 | 青虫が羽化して紋白蝶になる |
最初に冬籠りの虫が出て、桃の花が咲き、最後に紋白蝶が飛び始める…まさに春の饗宴ですね!
啓蟄(けいちつ)のスピリチュアルな意味とは?
啓蟄(けいちつ)は二十四節気のひとつで、冬ごもりしていた虫たちが地上に這い出てくる時期を指します。毎年3月5日頃に訪れ、春の訪れを告げる重要な節目とされています。スピリチュアル的には、この時期には目覚め・再生・エネルギーの高まりといった象徴的な意味が込められています。
🌿 啓蟄のスピリチュアルなキーワード
- 目覚めと変化:冬の間に溜め込んでいたエネルギーが解放され、動き出すタイミング。
- 新たなスタート:新しい挑戦や決断をするのに適した時期。
- 地球のエネルギー上昇:大地が暖まり、波動が高まることで運気の流れも活発に。
- 直感が冴える時期:この時期にインスピレーションを受けやすく、スピリチュアルな気づきが増える。
🌸 啓蟄の開運アクション
🔹 家の中の浄化をする:冬の間に溜まった「停滞エネルギー」を掃除や換気で一掃すると◎。
🔹 外に出て自然に触れる:春の陽気を感じながら散歩すると、良い運気を取り入れられる。
🔹 新しいことを始める:この時期に始めたことはスムーズに進む傾向が。
🔹 断捨離をする:古いものを手放すことで新しいエネルギーが入ってくる。
🔹 瞑想やアファメーション:直感力が高まる時期なので、自己対話を意識すると良い気づきが得られる。
🌞 啓蟄の日にやってはいけないこと
❌ ネガティブな感情に囚われる:この時期は運気が活発に動くので、不安やイライラは手放すことが大切。
❌ 家にこもりっぱなし:外のエネルギーが活発になる時期にこもっていると、運気が停滞する可能性が。
❌ 怠ける・先延ばしにする:せっかくの新しいスタートの時期なので、行動することが開運の鍵に。
🐛 啓蟄のメッセージとは?
啓蟄は「目覚めよ、新しい自分へ!」というスピリチュアルなサインでもあります。
「何かを変えたい」「新しいことを始めたい」と感じているなら、今こそ行動に移すべきタイミングです。
また、虫たちが地上に出てくるように、あなたの中に眠っていた才能や想いも解放される時。啓蟄を迎えたら、心をオープンにして、新しいエネルギーを取り入れてみましょう✨
啓蟄の旬の食べ物と楽しみ方
啓蟄は、冬から春へと季節が移り変わる時期で、自然界も徐々に活気を取り戻し始めます。気温の上昇と共に、旬の食材が豊富になるこの時期には、春の訪れを感じさせる様々な食材が料理の主役になります。山菜、たけのこ、にしんなど、春らしい食材を使った料理を楽しむことで、季節の変わり目を味わい深く体験しましょう。
山菜
啓蟄には、ほろ苦い「ふきのとう」、粘り気が特徴の「わらび」、独特の食感を持つ「ぜんまい」など、若々しい山菜が旬を迎えます。これらは、春の訪れを感じさせる繊細な味わいが特徴。アクの強い山菜は、適切な処理を施すことで、その本来の美味しさを引き出せます。
たけのこの美味しさ
たけのこの旬は啓蟄から始まり、淡白でありながら豊かな食感を楽しめます。炊き込みご飯や若竹煮など、様々な料理に使える万能さも魅力。たけのこの料理は、春の食卓を豊かに彩ります。
さよりを味わう
さよりは、この時期に最も美味しい魚の一つで、その透明感のある身と淡白な味わいは、生で食べるのが最もおすすめ。さまざまな調理法で、さよりの魅力を存分に引き出しましょう。
にしんの伝統的な味わい
春を告げる魚として知られるにしんは、脂ののった豊かな味わいが特徴です。塩焼きや蒲焼き、にしんそばなど、多彩な料理でその味を楽しめます。
はまぐりの春の味
はまぐりは、この時期にぴったりの食材で、その柔らかな身と濃厚なうま味は、春の食卓を華やかにします。ひな祭りなどの春の行事にも欠かせない、縁起の良い食材です。
啓蟄の行事と春の花
菰はずし
啓蟄を迎えると、伝統的な行事「菰はずし」が行われます。これは冬期間、松の木を害虫から守るために巻かれた菰(わらで作ったマット)を取り除く作業です。春の暖かさと共に虫たちが活動を始めるこの時期、菰を外すことで害虫を駆除し、新たな季節を迎える準備をします。
春を呼ぶ雷、虫出しの雷
啓蟄には「虫出しの雷」と呼ばれる春雷が鳴り響きます。この雷音に驚いた冬眠中の虫たちが地中から這い出てくる様子を象徴しています。一過性の雷であり、自然界に春の訪れを告げるサインとして古来から親しまれています。
桃の花、春の象徴
啓蟄の季節は、桃の花が咲き始める時期でもあります。鮮やかなピンクの花びらが開花し、春の訪れを色鮮やかに告げます。七十二候でこの時期を「桃始笑」と表現し、桃の花の咲く様子を春の喜びとして捉えています。
かたばみ、春の訪れを告げる草花
かたばみも啓蟄に親しまれる草花の一つです。ハート形の葉と小さな黄色い花が特徴で、夕方には葉を閉じて眠るような姿を見せます。この植物は、春の温かな日差しの下で生き生きと成長し、春らしい風景を作り出します。

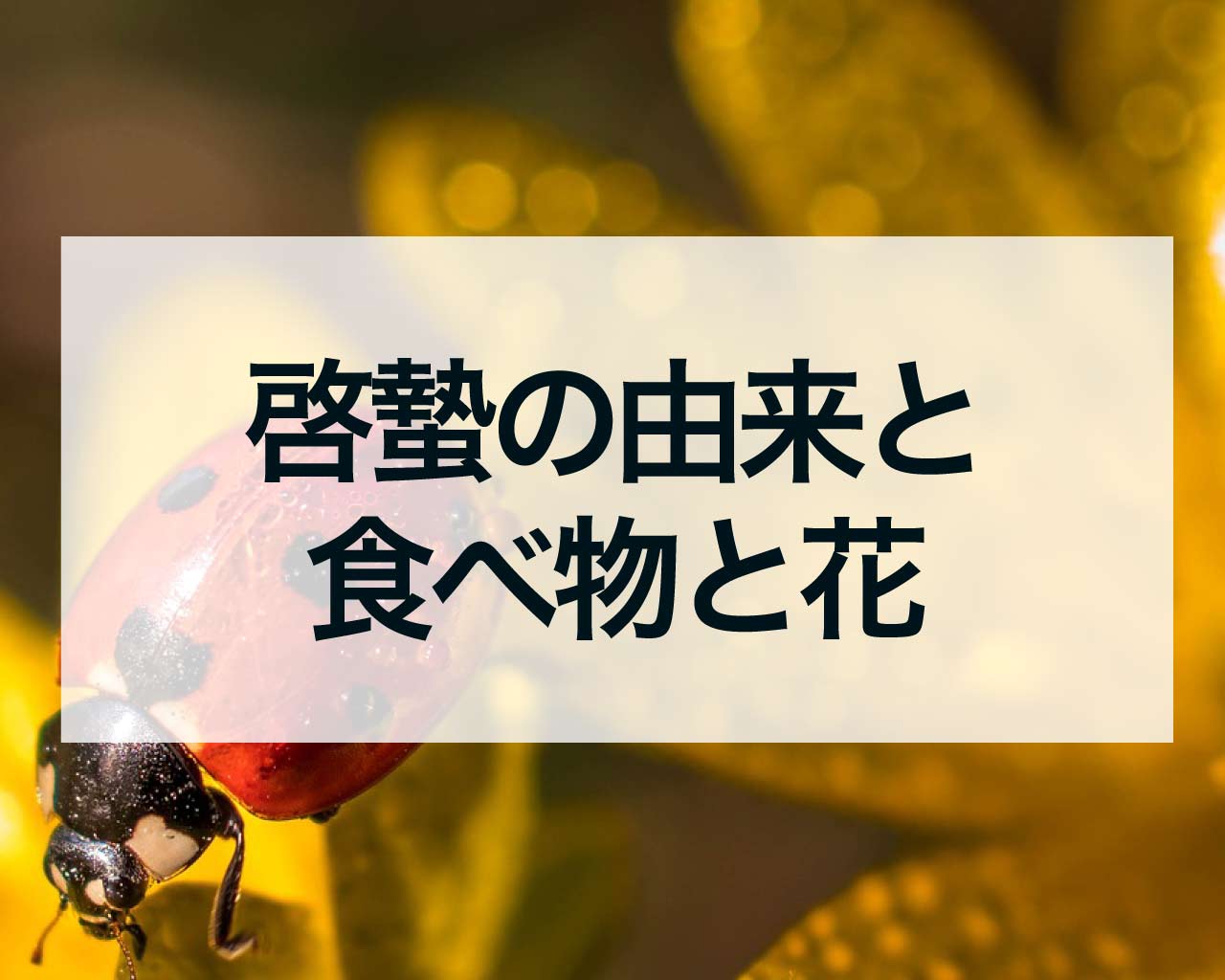


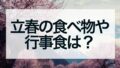

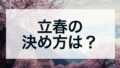
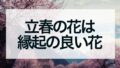
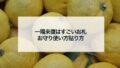
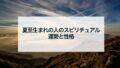
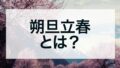

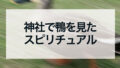
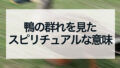
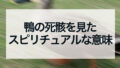
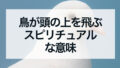
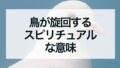
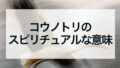
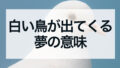
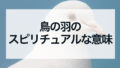
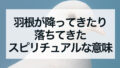
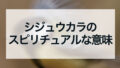

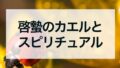
コメント