今年が厄年…という方もいるのではないでしょうか。でも厄年ってどうやって数えるの?厄の払い方ってどうしたらいいの?などの疑問を解決します。
男女それぞれの厄年と、その年にあたる生まれ年、西暦などを知りたい時に使ってくださいね。
2025年(令和7年)女の厄年早見表
厄年は数え年(数え年は現在の満年齢に、その年すでに誕生日を迎えられた方は「1」歳を、まだ迎えられていない方は「2」歳を加えた年齢が、今年の数え年となります)ですので、生まれ年を確認して注意しましょう。
女性の厄年は19才、33才、37才、61才にあります。2025年の厄年は下記になります。男性と女性では女性の方が厄年が多いです。
| 厄年分類 | 年齢 | 生年(西暦) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 18歳 | 2008年生まれ | |
| 32歳 | 1994年生まれ | ||
| 36歳 | 1990年生まれ | ||
| 60歳 | 1966年生まれ | ||
| 本厄 | 19歳 | 2007年生まれ | |
| 33歳 | 1993年生まれ | ※大厄※ | |
| 37歳 | 1989年生まれ | ||
| 61歳 | 1965年生まれ | ||
| 後厄 | 20歳 | 2006年生まれ | |
| 34歳 | 1992年生まれ | ||
| 38歳 | 1988年生まれ | ||
| 62歳 | 1964年生まれ |
2025年(令和5年)女の厄年、13才(幼児の厄)
これは幼児の厄年で、子供の厄年は数え年で1歳、4歳、7歳、10歳、16歳になる1年間となっています。
この子供の厄年齢は一般的なもので、他にもいろいろあります。この全てで厄払いをすることは稀で(七五三や100日参りなどと重なるため)、数え年で13歳の時に、「十三歳参り」として厄除けを行うというご家庭が多いです。
2025年(令和7年)女の厄年、19才
この厄年は数え年となっています。
本厄 20 平成19年生 (2007)満18歳
後厄 21 平成18年生 (2006)満19歳
2025年(令和7年)女の厄年、33才「女の大厄」
この厄年は数え年となっています。この厄年は「女の大厄」と言われて、最も大きな厄となります。一番問題が起きやすいので、他の厄年よりもお払いを受ける方が多いです。
本厄 33 平成5年生 (1993)満32歳
後厄 34 平成4年生 (1992)満33歳
2025年(令和7年)女の厄年、37才「女の小厄」
この厄年は数え年となっています。「女の小厄」と呼ばれる厄年です。
本厄 37 昭和64年/平成元年生 (1989)満36歳
後厄 38 昭和63年生 (1988)満37歳
2025年(令和7年)女の厄年、61才「老い厄」
この厄年は数え年となっています。「老い厄」と呼ばれる厄年で、これから老年に入る前にと受ける方が多いです。
本厄 61 昭和40年生 (1965)満60歳
後厄 62 昭和39年生 (1964)満61歳
2025年(令和7年)男の厄年早見表
男性の厄年です。男性には厄年が数え年で25歳、42歳、61歳の時にあります。この他に幼児の厄は男女ともに同じです。
| 厄年分類 | 年齢 | 生年(西暦) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 24歳 | 2002年生まれ | |
| 41歳 | 1985年生まれ | ||
| 60歳 | 1966年生まれ | ||
| 本厄 | 25歳 | 2001年生まれ | |
| 42歳 | 1984年生まれ | ※大厄※ | |
| 61歳 | 1965年生まれ | ||
| 後厄 | 26歳 | 2000年生まれ | |
| 43歳 | 1983年生まれ | ||
| 62歳 | 1964年生まれ |
2025年(令和7年)男の厄年、13才(幼児の厄)
これは幼児の厄年で、子供の厄年は数え年で1歳、4歳、7歳、10歳、16歳になる1年間となっています。
この子供の厄年齢は一般的なもので、他にもいろいろあります。この全てで厄払いをすることは稀で(七五三や100日参りなどと重なるため)、数え年で13歳の時に、「十三歳参り」として厄除けを行うというご家庭が多いです。
2025年(令和7年)男の厄年、25才
この厄年は数え年となっています。
本厄 25 平成13年生 (2001)満24歳
後厄 26 平成12年生 (2000)満25歳
2025年(令和7年)男の厄年、42才「男の大厄」
この厄年は数え年となっています。「男の大厄」と呼ばれる厄年で、厄払いを受ける方が多いです。
本厄 42 昭和59年生 (1984)満41歳
後厄 43 昭和58年生 (1983)満42歳
2025年(令和7年)男の厄年、61才「老い厄」
この厄年は数え年となっています。「老い厄」と呼ばれる厄年で、これから老年に入る前にと受ける方が多いです。
本厄 61 昭和40年生 (1965)満60歳
後厄 62 昭和39年生 (1964)満61歳
厄年と数え年
厄年は「数え年」で数えます。なので、パッと見ると自分の年齢とは違う気がしてしまいますが、生まれ年を見ると自分の年齢だったりします。
「数え年」とは
「数え年」とは生まれてからその人が過ごした年を表す年齢のことです。
数え年(かぞえどし)とは、満年齢などに対する年齢の表現方法の一種で、生まれてから関わった暦年の個数で年齢を表す方法(生まれた年を「1歳」「1年」とする数え方)である。
そのため、数え年で考えると赤ちゃんは生まれた時がすでに1歳となります。お正月がくると1つ年をとることになるので、12月31日に生まれた赤ちゃんは、次の日の元旦には2歳になってしまうわけです。
数え年の計算方法
数え年は現在の満年齢に、その年すでに誕生日を迎えられた方は「1」歳を、まだ迎えられていない方は「2」歳を加えた年齢が、今年の数え年となります。
子供の厄年について
子供にも厄年が存在します。一般的には数え年で1歳、4歳、7歳、10歳、16歳になる1年間となっています。
・令和3年(2021年)⽣まれ
・平成27年(2015年)⽣まれ
・平成24年(2012年)⽣まれ
・平成21年(2009年)⽣まれ
この厄年を全てお払いすることは稀です。
子供には百日参りや七五三参りなどがあるため、重なってしまうからのようです。
多くは「十三歳参り」のみ行っています。
これは12歳で干支が一回りするので、一区切りとして考えるためです。
幼児の厄も大人の役と同じで、神社に出向き厄除けの祈祷をしていただきましょう。
十三歳参りとは
十三歳参りは、数え年で13歳の年に神社へ出向き厄除けの祈祷をしていただく儀式です。一般的には3月13日~5月13日の間に行いますが、地域によっては10月・11月頃に行うところもあります。
厄払いの方法
神社に出向き厄除けの祈祷をしていただくのが、一般的な厄払いになります。
神社で厄払いをしてもらう時期や服装
厄払いの時期については、何月ごろでなければならないという決まりはありません。よく言われるのは厄年になった年の早い時期の方がよいというものです。
- 正月の初詣の時に一緒に行う
- 節分(旧正月)までの間に行う
- 誕生日に一緒に行う
というのが一般的です。だからと言って、厄年の最後に行うのが悪いということではありません。厄年が終わりそうになっても、気になったら厄払いをしましょう。
個人の方が神社で行う場合は特別な予約などは不要なことが多いです。ただ、神社によっては混み合うこともありますので、電話で聞いてみるのがいいですね。
厄払いの服装に決まったものはなく、普段着で十分ですが、露出のある服装や裸足などはやめた方がいいでしょう。
神社に渡す厄払いのお礼の仕方
厄払いの料金相場は、おおよそ3000円~1万円が相場(地域や神社によって異なる)です。神社によっては価格が決まっています。先に聞いておくと安心です。
お礼の渡し方は紅白の水引きのついたのし袋か、白い無地の封筒を使って終了後に渡すのが一般的です。
水引は蝶結びを使い、結び切りののし袋は使いません。
神社によっては渡し方が決まっていますので確認しておきましょう。のし袋・封筒の表書きは、お寺では「お布施」としますが、神社では「初穂料(はつほりょう)」または「御玉串料」と書きます。
厄年の人に七色のものを贈る
厄年の人に7色のものを贈る(もしくは自分で購入してつける)という習慣があります。これで厄除、厄払いになると言われています。
これには下記のような理由があります。
七は八、九の前だから、厄除になる
これは言葉の語呂合わせで、八、九(ヤク)の前は七なので七色のものを身につければ厄除ということです。
「七難即滅 七福即⽣」から7色のものを身に着ける
「七難即滅 七福即⽣」は七難である「⽕難、⽔難、⾵難、旱魃(かんばつ)などの旱害(かんがい)、盗難、太陽の異変、星の異変が消滅して、七福である「寿命、⼈望、清廉、⼤量、威光、有福、愛敬」が生まれるという意味です。
この七から七色のものを身に着ける…という風習が生まれたようです。
七福神から七色のものを身に着ける
七福神を七色に見立てて、そのパワーで厄除という意味です。
- ⻑寿をあらわす寿⽼⼈
- ⼈望をあらわす福禄寿
- 清廉(正直)をあらわす恵⽐寿
- ⼤量(商売繁盛)あらわす布袋尊
- 威光をあらわす毘沙⾨天
- 有福(財富)をあらわす⼤⿊天
- 愛敬をあらわす辨財天
芸能人は厄払いをしない
芸能人、特に俳優さんや歌舞伎役者さんは「厄=役」なので厄払いをしないんだとか…。芸能人は験を担ぐ方が多いので、役がなくなると困るということでしょう








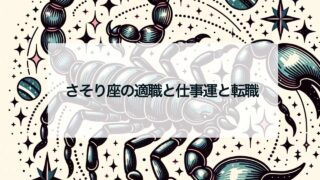


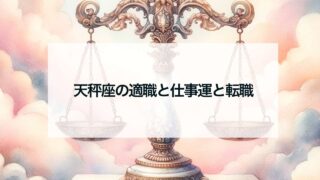

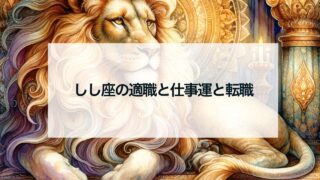

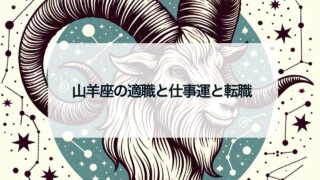
コメント