七夕様の七月七日ごろは二十四節気で「小暑」と呼ばれます。
この時期はようやく梅雨が明け、本格的な夏到来となります。
小暑とは、意味
小暑(しょうしょ)とは毎年7月6日または7日にあたり、二十四節気の中の11番目の節気を指します。小暑は夏至の次に位置し、更なる暑さが到来する大暑へと向かう期間を表します。これは、暑さが本格化してくる初夏の時期を象徴しています。
二十四節気は太陽の黄経を等分し一年を24の期間に分けたものです。小暑は太陽黄経が105度のときになります。
小暑の意味
小暑には「少しずつ暑くなる」という意味があり、その名の通り、夏の暑さが本格化する直前の季節を指します。この時期になると、梅雨が終わりを告げ、初夏の象徴である蝉の鳴き声が聞こえ始める、まさに夏の訪れを実感できる期間です。
暦便覧の小暑
江戸時代に活動した常陸宍戸藩の第5代藩主であり、暦学者でもあった太玄斎(松平頼救)が著した暦についての指南書「暦便覧」では、「大暑来れる前なればなり」と記されています。これにより、小暑が「本格的な暑さが到来する前の期間」を意味することが理解できます。

小暑はいつ?
2026年は7月7日になります。
小暑(しょうしょ)の期間
二十四節気は固定した日付に基づいているわけではないため、年によって微妙に日付が変わることがあります。2024年においては、小暑は7月6日から始まります。そして、小暑の期間は次の二十四節気である大暑が始まる7月22日頃までの約15日間となります。
小暑と梅雨
この小暑である七月七日ごろはちょうど梅雨が明けるか明けないか、という微妙な時期になります。
雨の時期が過ぎて湿気を含んだ風が熱い、大地は濡れているのに空は突き抜けるように青く太陽がぎらついている…本格的な夏の到来を感じさせますね。
小暑の七十二候
「小暑」の「七十二候」です。真夏の象徴である熱い風が吹き込み、まだ涼しい朝に蓮が花開き始める様子は、この時期の日本の風情を感じさせます。都市部でも、例えば東京の上野公園の不忍池では早朝に蓮の花が見頃となります。また、鳥たちが子育てを始めるこの頃、私たちは公園などでその様子を見ることができます。これらの情景は、季節感を感じさせる大切な瞬間を表しています。
初候:温風至(あつかぜいたる)(7月7日〜7月11日頃)
この時期は「小暑」の初候にあたります。
「温風至」とは、夏の暖かい風が本格的に吹き始めるころという意味です。梅雨もそろそろ終わりが近づき、南から湿った温かい風が吹き込み、気温もぐっと上がります。夜でも蒸し暑さを感じることが多くなり、いよいよ夏本番への入り口です。体調管理が大切になるタイミングでもあります。
次候:蓮始開(はすはじめてひらく)(7月12日〜7月16日頃)
この時期は、「蓮(はす)の花が咲き始める頃」を表します。
**蓮の花は朝早く美しく咲き、昼には閉じてしまう神秘的な花。**池や沼に大きな葉とともに咲くその姿は、夏らしさと涼しさを感じさせてくれます。蓮は泥の中から美しい花を咲かせることから「清らかさ」や「成長」の象徴ともされ、古くから仏教とも深い関わりがある花です。
末候:鷹乃学習(たかすなわちわざをなす)(7月17日〜7月22日頃)
「鷹乃学習」とは、鷹の雛(ひな)が巣立ちのために飛ぶ練習を始める時期という意味です。猛暑の中でも、生き物たちは命のバトンをつなぐ準備をしています。鷹の子が親から狩りの方法を学び、独り立ちのための訓練を始める…そんな自然界のドラマが展開される時期です。自然の生き生きとした生命力を感じられる季節です。
小暑と暑中見舞いとお中元
小暑は、七夕様に隠れて比較的馴染みの薄い節気ではありますが、実は日本の日常生活と深く関わっている重要な時期でもあります。
近年では異常気象により梅雨明けが遅れたり、突如として猛暑が訪れたりと、厳しい夏を過ごすことが多くなっています。そんな中で、暑中見舞いやお中元を通じて互いの安否を確認し、お互いの思いやりを示すことは、非常に価値ある行為でしょう。
暑中見舞いと小暑
小暑にやることは暑中見舞いです。暑中見舞いは、通常小暑から立秋までの間に出すものとされています。ただし、小暑を過ぎても梅雨が続いている場合は、天候を見て梅雨明けを待ってから暑中見舞いを出すことが一般的です。
なお、立秋を過ぎてしまった場合は、季節に合わせて「残暑見舞い」と称するようにします。
小暑とお中元
小暑の時期は家族や友人、親しい人やお世話になっている人、会社の上司への挨拶や感謝の意を伝える大切な機会でもあります。お中元の贈り物をするのも小暑の時期の一般的な習慣です。
お中元は小暑から7月15日くらいを目安に送りましょう。
小暑と七夕と土用の丑の日、食べ物
この小暑の時期に食べるものや行事食をご紹介します。
小暑の食べ物、七夕のそうめん
小暑は毎年七月七日か六日になりますので、ちょうど七夕と重なります。そのため、小暑の食べ物といえば七夕のそうめんとなるでしょう。
この時期はムッと湿った暑さで、食欲も落ちがちな時期です。さっぱりとした素麺を食べて元気を出しましょう。
小暑の食べ物、土用のうなぎ
この小暑は七月七日から次の大暑まで、約15日間あります。そのため夏の土用と重なることも…。
夏の土用といえばやはりうなぎ!これも夏バテにはぴったりの食べ物ですね!
夏の土用は一般的に立秋前の18日間を指します。これは通常、毎年7月20日頃に始まります。そして、その土用の期間中に訪れる「丑の日」が特に有名で、「土用丑の日」として広く知られています。 暑さの盛りに来る土用丑の日には、体調を崩さないようにと、うなぎや土用しじみ、土用もち、土用卵といった栄養価の高い食べ物を摂る習慣が日本全国に広まっています。 また、一年によっては丑の日が2回訪れることもあり、これらはそれぞれ「一の丑」、「二の丑」と呼ばれます。
小暑に見頃の花
小暑の時期(7月7日〜7月22日頃)は、夏本番を感じさせる華やかな花が多く咲き誇ります。この時期ならではの美しい花々をいくつか紹介します。
蓮(はす)
池や沼で大きな葉とともに咲く蓮の花は、まさに小暑のシンボル的存在。早朝に咲き、昼前には閉じる幻想的な姿は、涼やかさと清らかさを感じさせてくれます。
朝顔(あさがお)
小学生の夏休みの観察でもおなじみの朝顔は、涼しい朝に花を咲かせます。青や紫、ピンクなど色とりどりの花が夏の空気によく映えます。
百合(ゆり)
真っ白や黄色、オレンジの花を咲かせる百合も、この時期に見頃を迎えます。大きな花と甘い香りが特徴的です。
桔梗(ききょう)
涼しげな青紫色の花が美しい桔梗も、小暑から夏の間に咲きます。星形の花がさりげなく上品な雰囲気を添えてくれます。
夾竹桃(きょうちくとう)
ピンクや白、赤の華やかな花を咲かせる夾竹桃は、公園や道路沿いなどでもよく見かけます。暑さにも強い花です。
ラベンダー
小暑の頃にはラベンダーも見頃を迎えます。紫色の小さな花が房状に咲き、爽やかな香りが広がるのが特徴です。ラベンダーは北海道などの涼しい地域を中心に栽培されており、リラックス効果のある香りは夏の疲れた心や体を癒してくれます。
このような夏の花々は、見ているだけで涼やかな気持ちになり、心にも元気を与えてくれます。身近な場所でも楽しめるので、ぜひ探してみてください。




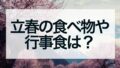

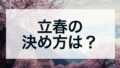
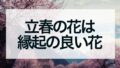
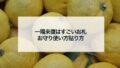
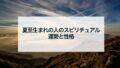
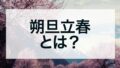

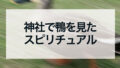
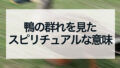
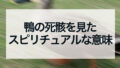
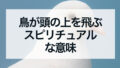
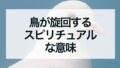
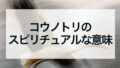
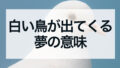
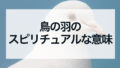
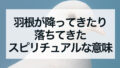
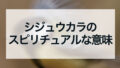


コメント