二十四節気で最も暑い大暑についてです。2026年は7月22日が大暑となります。
大暑とは
大暑は二十四節気の一つで、一年で最も暑い時期を意味してます。
大暑の期間は、夏の最も暑い時期を示し、これに続くのが「立秋」で、暦上では秋の始まりを示します。また、大暑の期間は夏の土用や土用の丑の日と重なることが多いです。夏の土用とは、立秋の前の約18日間のことで、体調を整えるためにうなぎを食べるという風習があります。
大暑は、夏の間に友人や親戚などに送る「暑中見舞い」の期間とも一致します。暑中見舞いは、暑さを乗り切るための気遣いの一環で、立秋以降は「残暑見舞い」と呼ばれます。
大暑はいつ?
大暑は2026年7月22日になります。
大暑の期間
大暑は、小暑が終わった次の日から立秋の前日までの期間となりますので、2026年7月22日から8月7日までを指します。ただし、日付は固定されていないため、毎年少しずつ前後することがあります。
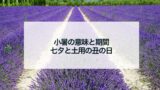
大暑の七十二候
大暑の期間は、7月22日頃から8月6日頃までで、この期間の「七十二候」を紹介しますね!
大暑の七十二候、初候「桐始結花」(7月22日〜7月26日頃)
桐始結花桐「きりはじめてはなをむすぶ」:桐始結花桐の花が(来年の)蕾をつける
桐は初夏に繊細な紫色の花を咲かせ、現在、真夏の高まりと共に、長さ約3cmの卵形の果実をつけています。これらの果実の中には、羽根のような翼を持つ種子がぎっしりと詰まっています。これらの種子は風をキャッチし、遠くへと飛散していきます。
大暑の七十二候、次候「土潤溽暑」(7月27日〜8月1日頃)
土潤溽暑「つちうるおうてむしあつし」:土が湿って蒸暑くなる
「土熱れ(つちいきれ)」は、地面が強烈な陽光を受けて発熱する現象や、その熱自体を指す表現です。この表現は、特にこの時期に感じられる湿度と熱さを象徴しています。また、「溽暑(じょくしょ)」という言葉は、湿度が高くじっとりと暑い状況を表します。この語は、旧暦6月(陰暦6月)の別名としても使われ、その月の特徴的な気候を反映しています。
大暑の七十二候、末候「大雨時行」(8月2日〜8月6日頃)
大雨時行「たいうときどきにふる」:時として大雨が降る
「大雨時行」は夏の終わりを告げる候で、この時期には集中豪雨や突然の夕立が特徴的です。鮮やかな青空に対照的に、急に発生する巨大な入道雲が、突如として雷鳴と共に強烈な夕立へと変わります。この激しい雨が、渇きを覚えていた大地に十分な水分を与えて潤します。
大暑にやること
大暑は一年の中でも特に暑い時期を指し、この時期の過ごし方や食事にも工夫が求められます。
大暑にやること、土用の丑の日に「う」のつくもの食べる
大暑は、一年で最も暑さが厳しい時期を表す節気であり、この時期には日頃の疲れを癒し、体調を整えるためのさまざまな行動が推奨されます。特に、旬の食材を活用した食事や適度な休息、涼を求める行動などが重要とされます。
一方、土用の丑の日には「う」のつく食べ物を食べるという習慣があります。これは江戸時代の商人の戦略から生まれたもので、主に「うなぎ」を食べる習慣が知られていますが、「う」のつく他の食べ物を食べるのも良いとされています。精がつくなら鰻より牛の肉で焼肉を食べるのもいいでしょう。
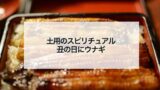
例えば、「うり(冬瓜やスイカ)」、「うどん」、「うに(海胆)」なども良い選択肢です。「う」のつく食べ物を食べることで、暑さで弱ってしまった体力を回復し、夏バテを防ぐと言われています。
これらの食事は、その時期の体調や暑さに対する対策として考えられたもので、健康維持の一環として取り入れてみると良いでしょう。
最近では、伝統的な食材や料理が見直されている傾向にあり、「土用餅」などが再注目されています。土用餅は、土用の期間中に食べることで体調を整えるとされています。また、鰻などの土用の丑の日に食べるものだけでなく、土用卵や土用しじみなど、他の食材も体調維持に役立つとされています。
この時期はしんどい方多いですよね…。季節の変わり目ですし。
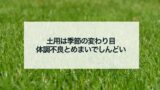
大暑にやること、暑気払いに冷麦やそうめんスイカを食べる
また、最も暑いこの時期は、暑さを和らげる食べ物を摂るのも重要です。伝統的な暑気払いの食事としては、冷麦やそうめん、ビール、さまざまな種類の瓜(西瓜、胡瓜、冬瓜、苦瓜、南瓜など)、そして涼感を感じるかき氷や氷菓子などがあります。また、甘酒などの発酵食品は体調管理にも役立ちます。
大暑にやること、風鈴やうちわで涼をとる
さらに、暑さを感じるのは身体だけではありません。視覚や聴覚などの五感を通じて感じる涼しさも重要です。風鈴の音やすだれの見た目、団扇の風など、伝統的な夏の風物詩が涼感を提供します。
大暑にやること、夏祭りや花火大会を楽しむ
この時期はまた、夏祭りや花火大会が行われることが多く、浴衣を着る機会も多くあります。祭りや花火の豆知識を学び、楽しむことも大暑の過ごし方の一つと言えるでしょう。
大暑のスピリチュアルな意味
大暑は、その名の通り年間で最も暑さが厳しい時期を指します。これは一般的に7月中旬から下旬にあたります。スピリチュアルな観点から見ると、この期間はエネルギーが最も活発になる時期とも言われています。自然のエネルギーが最高潮に達し、生命力が最も強まるこの時期は、活動的で創造的なエネルギーを引き出すのに最適な時期とも考えられています。
また、大暑の期間は、自然と共に人間自身も高まるエネルギーに対応するため、自己啓発やスピリチュアルな成長に向けた時間とされることがあります。そのため、ヨガや瞑想など、心身の調和を促す活動を行うのに良い時期ともされています。
しかし、エネルギーが高まる一方で、この時期は暑さが厳しく、身体的な疲労や夏バテも引き起こしやすい時期です。そのため、適切な休息や栄養摂取、水分補給など、自己の健康管理にも意識を向けることが重要です。
以上のように、大暑は物理的な季節の変化だけでなく、スピリチュアルなエネルギーの流れや自己の成長についても示す重要な時期と考えられています。
大暑の花火のスピリチュアルな意味
花火は、その鮮やかな色彩と一瞬で消えてしまうはかなさから、多くの文化で特別な象徴として扱われてきました。そして、花火は夏の象徴でもあります。特に日本では、大暑の時期に多くの花火大会が開催されます。これにはスピリチュアルな意味合いも含まれています。
1つには、花火は浄化の象徴ともされます。花火が打ち上げられると、その閃光と共に、視覚的な驚きと心地良い驚愕が起こります。そしてそれは、日々の生活の中で溜まったネガティブなエネルギーやストレスを一掃し、心を浄化すると考えられています。
また、花火は変容の象徴でもあります。火薬が瞬間的に反応し、美しい光と音を発するその過程は、人生の変化や成長を象徴しています。つまり、夏の高まりとともに、自分自身も新しいステージに進む準備をするというメッセージを感じ取ることができます。
さらに、花火の一瞬の美しさは、一瞬で消えてしまう人生のはかなさ、そしてそれぞれの瞬間を大切に生きることの大切さを教えてくれます。
したがって、大暑の時期の花火は、自分自身の浄化や変容、そして瞬間を大切にするというスピリチュアルなメッセージを伝えてくれると言えます。

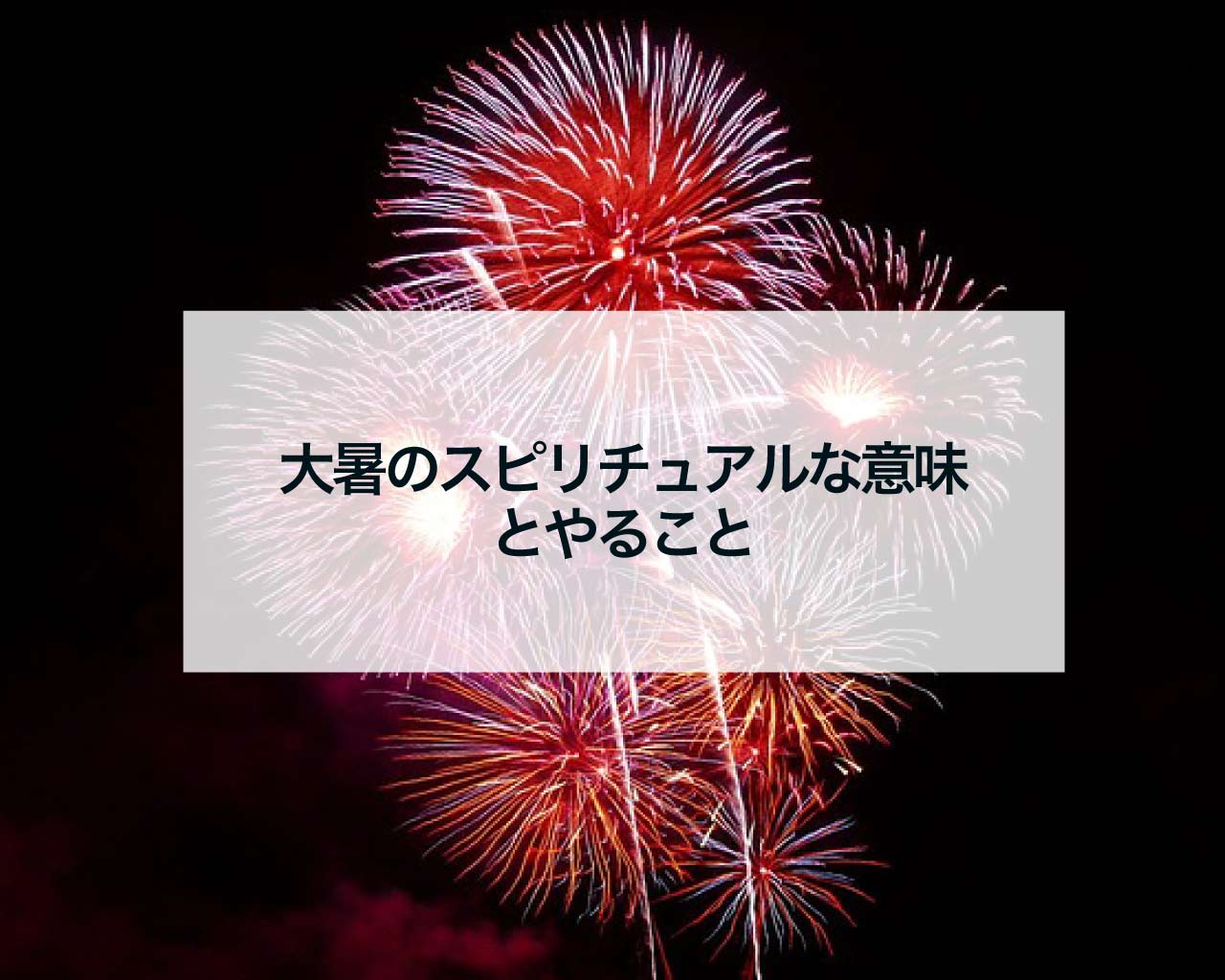



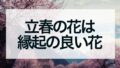
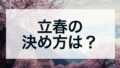
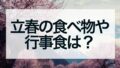
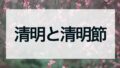



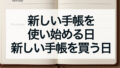
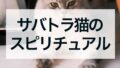
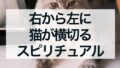
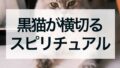
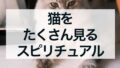
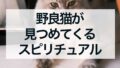

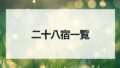
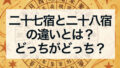



コメント