白露の時期になると、秋の気配が身近に感じられるようになります。季節の変わり目、特にこの時期は体調を崩しやすいため、古くからの知恵や食文化を取り入れて、心と体のケアを心がけましょう。白露や秋の七草を知ることで、自然のリズムに合わせたより豊かな生活が送れるかもしれません。
白露(はくろ)とは
「白露(はくろ)」とは、日本の24節気の一つで、毎年9月7日から9月9日の間にあたります。2026年の白露は9月7日に設定されています。この頃になると、草木に白い露がつくことからこの名が付けられました。日中はまだ暑さが残ることもあるが、朝晩は少しずつ涼しさを感じ、秋の気配が訪れ始める時期です。
季節の変わり目は、体調を崩しやすい時期と言われています。特に、暑さと涼しさが交互に訪れるこの頃は、体がその変化に対応しにくくなることがあります。そこで、日本の古来からの暦や節気を意識することで、自然のリズムに合わせた生活を送ることがオススメです。
白露(はくろ)とは?その意味と特徴
「白露」は、「二十四節気」の一つとして知られ、秋を象徴する重要な節気です。秋を代表する節気には、「立秋」、「処暑」、「白露」、「秋分」、「寒露」、「霜降」の6つがあり、中でも白露はその3つ目に位置し、真夏の暑さから少しずつ遠ざかり、秋の深まりを感じる節目として注目されます。
江戸時代の記録から学ぶ白露の意味
江戸時代に刊行された『暦便覧』という暦の解説書に、「陰気ようやく重なりて露こごりて白色となれば也」という記述が見られます。これを現代の言葉に置き換えると、「涼しい気候が徐々に増え、暑さを上回り始めると、水蒸気が結露となり、その露が白く見える」という意味合いになります。
白露の季節の象徴:露
節気の「白露」には「露」という文字が含まれています。もちろん、露自体は年中見られるものですが、秋の時期は特に気温の変動が大きいため、結露が多く見られる時期でもあります。また、日本の文学、特に俳句や短歌の世界では、露は秋の代表的な季語として取り上げられています。
2026年の秋の節気
- 立秋:詳しくは「立秋とは?意味や由来、風習などを紹介」を参照。
- 処暑:2026年は8月22日。その詳細は「処暑とは2026年は8月22日」をご覧ください。
- 秋分:2064年は9月22日。詳しくは「秋分の日とは?2026年は9月23日」をチェックしてみてください。
二十四節気と白露のスピリチュアル
日本の文化や風情と深く結びついているのが、二十四節気という概念。太陽の運行や季節の変動を24の節目で表現し、長い間日本人の生活の中に根付いてきました。
二十四節気の起源
地球上の気温は太陽の高さによって変化し、季節が形成されていきます。さらに、月の引力により潮の満ち引きも起こります。これらの天体の動きは、私たち人間や他の生物、植物の生活に大きな影響を与えています。
日本では明治6年(1873)まで、太陰太陽暦を主に使用していました。この暦は月の運行や太陽の動きを組み合わせたもので、「旧暦」とも呼ばれます。二十四節気は、この旧暦に基づいて1年を24の時期に分けるものです。現代でも、この古い暦や節気の感覚を意識することで、日本の四季の移ろいを深く味わうことができるでしょう。
二十四節気「白露」の季語について
時は二十四節気の「白露」。9月初旬から中旬にかけて、日々の温度差が増してきます。この時期、涼しい朝には草花の葉や花弁に露が顕著に結ぶ景色を目にすることができます。
この微細な水滴は、湿度が高い空気が夜間の冷気と接触し凝縮されることで生まれます。そして、その露が早朝の光を受けてきらきらと輝く様は、まさに自然の芸術です。
古の日本人は、この清冷な露を「白露」と称えました。また、露の美しさを詠んだ言葉や季語は多数存在します。「しらつゆ」はその代表的なもので、秋の深まりを象徴する季語として詠まれてきました。
「露華」「露珠」「銀露」「月露」、「月の雫」…これらはすべて、細やかな露の美しさやその瞬時の輝きを表現する言葉たち。特に「玉露」は、露の滴を美しい玉のように見立てた、繊細で詩的な表現です。
白露の時期は、自然が奏でる季節の移ろいを感じる大切な時間。日常の喧騒から一歩離れ、朝の露を楽しむことで、秋の深まりや自然の美を再認識することができるでしょう。
秋の七草
秋の節気「白露」の頃には、秋の七草が咲き始めます。しかし、その前に「春の七草」を思い起こしてみましょう。春の七草は、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロのことを指し、正月の暴飲暴食からの回復を助けるために、1月7日に七草がゆとして食べられます。
対照的に、秋の七草はそれほど知名度が高くありませんが、歌人・山上憶良が『万葉集』に詠んだ歌に由来しています。具体的には、ハギ、ススキ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、そして諸説ある中で桔梗が挙げられます。これらの草花は、自然界での控えめな美しさを持つものが多いです。
秋の七草は、特に都市部では見る機会が少ないかもしれませんが、植物園や公園での展示を探すことで、その魅力に触れることができます。
- ハギ(萩) 日本の秋を象徴するハギは、庭木としても人気があります。ヤマハギが代表的ですが、他にミヤギノハギやイヌハギなどの種類があります。愛らしい紅紫色の花を咲かせることが多いですが、白い花を持つものもあります。生薬としての用途は特にありませんが、その美しい花で目を楽しませてくれます。
- ススキ(尾花) ススキは日本の風情を感じさせる植物で、日本各地の山や河原に自生しています。幽霊の正体と関連することわざや童謡にも登場するほど、日本人には馴染み深いです。かやぶき屋根の材料や十五夜の飾り物としても用いられます。
- クズ(葛) 荒れ地に自生するツル性の植物で、落ち着いた赤紫色の花が特徴的です。特にクズの根、葛根は生薬「葛根湯」の原料として知られています。また、この根から取得されるでんぷんを利用したくず粉は、くず餅やくず湯などの食品に用いられます。
- ナデシコ(撫子) ナデシコの名前は「大和撫子」として日本女性の美しさを例える言葉としても用いられます。多彩な色合いの花を持つこの草は、生薬としても利用されることがあります。セキチクという種類は、中国原産ですが日本でも人気があります。
- オミナエシ(女郎花) 小さな黄色い花が特徴のオミナエシは、花だけでなくつぼみや茎も黄色いため、長く観賞できます。「女を圧す」という語源を持つこの花は、日本の秋の風情に合ったものとして知られます。根や花枝は生薬としても利用されます。
- フジバカマ(藤袴) 淡い青紫色の花が特徴のフジバカマは、河原に自生しますが、近年は絶滅が危惧されています。この花の香りは、乾燥すると桜餅のような甘い香りを放ちます。このため、香料としても利用されることがあります。
- キキョウ(桔梗) キキョウの星形の青紫色の花は、秋の風情を感じさせるものです。この草の根は、生薬や「桔梗湯」としても利用されます。
夏から秋への移り変わりの季節は、日本の風土や文化を再認識する絶好の機会です。忙しい日常の中で、これらの植物たちが季節の移ろいを感じさせてくれることでしょう。




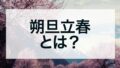
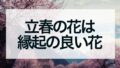
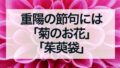
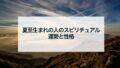
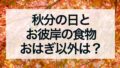
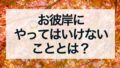
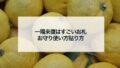
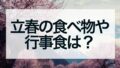
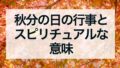
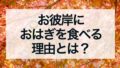
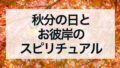
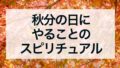
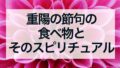
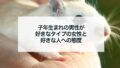

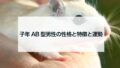


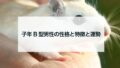





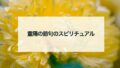
コメント