2026年の酉の日は、11月7日が一の酉、11月19日が二の酉です。酉の市は、毎年11月の酉の日に、酉にまつわる神社で開催される縁日です。酉の市では、縁起物の熊手などの露店がたくさん並び、1年の無事を報告し、新年の開運招福や商売繁盛を祈願します。2026年の酉の市は、新宿の花園神社や浅草などで開催されます。花園神社では、前夜祭と本祭の2日間にわたって行われ、熊手店や屋台などが200店舗以上立ち並びます。
2026年の酉の市はいつ?
2026年の酉の市は
| 酉の市 | 日付 | 日干支 |
|---|---|---|
| 一の酉 | 2026年11月7日(土曜日) | 乙酉いつゆう(きのととり) |
| 二の酉 | 2026年11月19日(木曜日) | 丁酉ていゆう(ひのととり) |
| 三の酉 | なし |
となっています。
酉の市とは
日本には数多くの祭りが存在しますが、特に11月に行われる「酉の市」は商売繁盛や開運を祈願する祭りとして、多くの人々に親しまれています。
酉の市について
酉の市は、毎年11月の酉の日に行われる祭りで、大鳥神社や鷲神社といった、商売繁盛の神として知られる神社でのお祭りです。この祭りでは、おかめの面や小判をあしらった縁起の良い熊手などが売られる露店が立ち並び、賑わいを見せます。
「一の酉」「二の酉」「三の酉」
酉の市は一の酉から三の酉までという3日間に分かれて行われます。それぞれの日を「一の酉」「二の酉」「三の酉」と呼ぶのが一般的です。伝承によれば、三の酉まである年は火事が多いとも言われていますので、注意が必要です。
酉の市は、日本の伝統的な祭りとして長い歴史を持つものの一つです。商売繁盛や開運を祈願するこの時期、神社は多くの参拝者で賑わいます。縁起物の熊手やおかめの面を手に入れ、新しい1年を迎える準備をしませんか?
酉の市の由来と歴史
日本には四季を彩る数々の伝統的な祭りがありますが、11月の「酉の市」は特に商売繁盛を祈願する祭りとして多くの人々に親しまれています。その歴史と由来を紐解いていきましょう。
酉の市の始まり
酉の市の起源は、日本武尊(やまとたけるのみこと)が東夷征討の勝利を祝し、松の木に熊手をかけてお礼の祭りをしたという伝説にあります。その際、祭りが行われた日が「酉の日」だったため、この日が神社の祭礼日となり、後に酉の市として定着したと言われています。
酉の市、江戸へ
最初の酉の市は、江戸時代の花又村(現在の東京都足立区花畑)の大鷲神社での収穫祭として始まりました。近在の農民たちはこの神社の鎮守、「鷲大明神」に収穫の感謝を捧げ、その日、奉納された鶏は浅草寺に運ばれ、観音堂前で放たれたという伝承が残っています。
江戸時代、この祭りは急速に人気を集め、浅草の鷲神社でも行われるようになりました。特に浅草の鷲大明神は、近隣に新吉原があったことから、非常に多くの人々が訪れ、酉の市は大変な盛況を見せました。
酉の市の風習
酉の市には「一の酉」「二の酉」「三の酉」という3つの日がありますが、これは日本の暦の巡りで酉の日が年に2回ある場合と3回ある場合があるためです。特に「三の酉」まである年は、火事が多いとされ、火の用心が特に重視される風習があります。
酉の市は、日本の伝統文化を色濃く反映する祭りの一つです。始まりの地である花又村から、浅草の鷲神社まで、この祭りは多くの人々に親しまれ、長い歴史を通じてその魅力を伝え続けています。
有名な酉の市の神社
有名な酉の市の神社とその特徴を表形式でまとめました。
| 神社・寺名 | 所在地 | 特徴・説明 |
|---|---|---|
| 大鷲神社 | 東京都足立区 | 江戸酉の市の発祥の神社 |
| 鷲神社 | 東京都台東区 | 関東三大酉の市のひとつ。日本最大の酉の市、浅草酉の市が開催される |
| 酉の寺・長國寺 | 東京都台東区 | 浅草酉の市の発祥の寺 |
| 花園神社 | 東京都新宿区 | 合祀された大鳥神社の祭り。関東三大酉の市のひとつ |
| 大國魂神社 | 東京都府中市 | 境内末社の大鷲神社の祭り。関東三大酉の市のひとつ |
| 練馬大鳥神社 | 東京都練馬区 | – |
| 大森鷲神社 | 東京都大田区 | – |
| 鷲宮神社 | 埼玉県久喜市 | 大酉祭の元祖 |
| 熊野神社 | 群馬県前橋市 | – |
| 金刀比羅大鷲神社 | 神奈川県横浜市 | 酉の市は横浜市の無形民俗文化財 |
| 大鳥大社 | 大阪府堺市西区 | 酉の市は関東が中心。熊手市や夜の屋台は無い |
酉の市で熊手を買うやり方と飾り方
酉の市とは、商売繁盛や招福を祈願するための伝統的な祭りで、縁起熊手が名物として知られています。この熊手は、福や富をかき集める象徴としての役割を果たしています。今回は、酉の市の縁起熊手の購入から飾り方までを解説していきます。
酉の市の縁起熊手とその魅力
酉の市の縁起熊手は、お多福、鶴、亀、大入り袋、打出の小槌、鯛、米俵、大黒様、大判小判、宝船、巻物、松竹梅、福笹など、さまざまな縁起物で飾られています。もともとは農具として売られていた熊手が、時とともに商売繁盛や招福の象徴として発展してきました。
熊手の買い方
- 値段を確認する: まず、お店の人に熊手の値段を尋ねます。
- 値切る: 値切ることが縁起のいいスタート。一度、二度と値切り、頃合いを見て商談成立を目指します。
- ご祝儀の心遣い: 実際には最初に聞いた値段で支払い、値切った分のおつりはご祝儀として渡します。これにより、売り手も買い手も満足する粋なやり取りが成立します。
この独特の購入方法は、商談のプロセスそのものが楽しみの一部となっており、酉の市を一層楽しむことができます。
熊手の持ち帰り方と飾り方
購入した縁起熊手は、大きな福をかき込む象徴として、高々と掲げて持ち帰ります。自宅に戻ったら、玄関や入り口に向けて、少し高めの位置に飾るか、神棚に供えてお正月を迎えます。この飾り方には、家庭への繁盛や福を招く力があると言われています。
酉の市は、新年を迎える前の繁盛と福を祈る大切な行事です。この期間に縁起熊手を購入して家に飾ることで、新しい年の繁栄と幸運を手に入れることができるでしょう。商談の楽しみから縁起熊手の飾り方まで、酉の市を存分に楽しんでみてください。


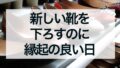
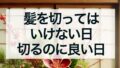
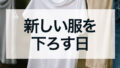



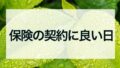
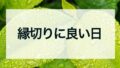
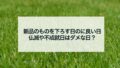




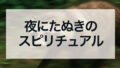
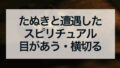
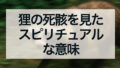



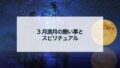


コメント