清明節に行われるさまざまな行事と、この季節に楽しまれる特別な食べ物に焦点を当てます。清明には、自然の恵みを受けた季節の食材を用いた料理が豊富に登場します。特に春の味覚は、この時期ならではの楽しみです。これらの食べ物には、それぞれ独特の意味が込められており、春の訪れを祝うとともに、健康や繁栄を願う願いが込められています。
清明とは、清明の意味と由来
清明(せいめい)という言葉は、「清浄明潔」を略したもので、すべてのものが清らかで活動的な様子を意味します。この時期は、多くの花が咲き誇り、木々が生命力に満ち溢れ、生き物たちが活発に動き回る季節です。また、清明は春を代表する季語としても用いられます。
二十四節気の流れでは、清明の直前に昼夜の長さが等しくなる「春分」があり、清明の後には作物に恵みの雨をもたらす「穀雨」が続きます。清明の期間は、一年の中で自然が最も清新で明るい時を迎え、万物が生き生きとしていることから、この名がつけられました。
2026年の清明の日付と期間
2026年の清明は4月5日に始まり、4月20日まで続きます。清明は二十四節気の一つで、約15日間隔で季節の変化を示すために24に分けられた周期の中の一つです。清明期間は、自然が最も清らかで生き生きとしている時期を表し、この期間は毎年4月5日頃から4月19日頃までとされていますが、太陽の動きに合わせて決定されるため、年によって1日程度の前後があります。
清明節の季節の食材
カツオ
清明の時期に獲れる初ガツオは、赤身の旨味とさっぱりとした味が特徴です。脂の乗りが控えめなため、刺身やたたき、レアカツとして楽しむのがおすすめです。
新玉ねぎ
春に収穫される新玉ねぎは、水分が豊富で辛味が少なく、やわらかな食感が楽しめます。サラダやマリネ、炒め物や煮物にすることで、春のみずみずしさを味わうことができます。
たけのこ
春の代表的な食材であるたけのこは、シャキシャキとした食感と独特の甘みが魅力です。新鮮なうちにアク抜きをして、若竹煮や土佐煮、たけのこごはんなどにすると、春の味覚を存分に楽しめます。
いちご
冬から春にかけてが本来の旬であるいちごは、そのまま食べるのはもちろん、ジャムやシロップにして長く楽しむこともできます。春には手頃な価格で入手しやすく、保存食としても活用できます。
中国の清明節
中国における清明節は、家族が集まり先祖のお墓参りと清掃を行う重要な祝日です。この時期に行われる墓参りは、故人への敬意と感謝の表現として古くから伝わる習慣です。
清明節や清明祭(シーミー)を通じて、故人を偲びながらも、春の訪れを感じる風習や食材を楽しむことは、自然の恵みと先祖への感謝を感じる大切な時期です。
沖縄の清明祭(シーミー)
沖縄では、清明節にちなんで「シーミー」と呼ばれるお墓参りの行事があります。参加者は豚肉、昆布、餅などを詰めた重箱を持参し、お墓の清掃やお参りを行った後、家族や親戚と共に食事を楽しむことで先祖を供養します。この風習は、故人への思いを新たにするとともに、家族の絆を深める機会となります。
沖縄の清明祭「シーミー」と春の季節行事
沖縄では清明の時期に、地元の方言で「シーミー」と称される清明祭が、家族や親戚が集まって華やかに行われます。この行事は「ウシーミー」とも呼ばれ、先祖のお墓参りとしての意味を持ちます。参加者たちは、先祖代々のお墓を掃除し、供え物を捧げた後、そこで共に食事を楽しむという形で先祖を供養します。お墓の周りで行われるこの宴会は、ピクニックのような雰囲気を持ち、伝統を重んじる沖縄の文化の中でも特に大切な行事の一つとされています。
清明祭の起源と「踏青」
清明祭は、中国の清明節が起源であり、「掃墓節」とも呼ばれています。これは、春の訪れと共に先祖の墓を清掃する習慣にちなんでいます。また、この時期は気候が穏やかで外を歩くのに適しているため、「踏青節」とも称されています。
日本には「踏青(とうせい)」という言葉があり、春の青草の上を歩き、自然の中で遊ぶことを意味します。この言葉は、踏青節から来ており、春の季語として用いられます。踏青は、自然との触れ合いを楽しむ春の伝統的な活動を象徴しています。
春を告げる代表的な植物たち
カタクリ:春の短い訪問者
カタクリは、ユリ科に属する多年草で、春のわずかな期間、淡い紫色の美しい花を咲かせます。この植物は「スプリングエフェメラル」とも呼ばれ、初夏に地上部が枯れて消え、翌春まで地下で生活する特性を持ちます。かつてはカタクリの根から取れるデンプンが片栗粉の原料として使われましたが、今日ではその役割をじゃがいもが担っています。
ヒエンソウ:清明を象徴する花
ヒエンソウはキンポウゲ科デルフィニウム属に属する植物で、「清明」という花言葉を持っています。花屋で見かけるデルフィニウムはヒエンソウの一種で、主に5月から6月にかけて水色や淡い紫色の花を咲かせ、その清らかな美しさで多くの人を魅了します。
レンゲソウ:春の風物詩
レンゲソウはマメ科の植物で、秋に発芽し、冬を越えて春にかけて赤紫色の小さく愛らしい花を咲かせます。土壌改良の効果があるため、かつては田畑に広く植えられ、春にはレンゲ畑が広がる風景が一般的でした。現在はその数は減少していますが、野原や土手で見ることができ、春の訪れを感じさせてくれます。

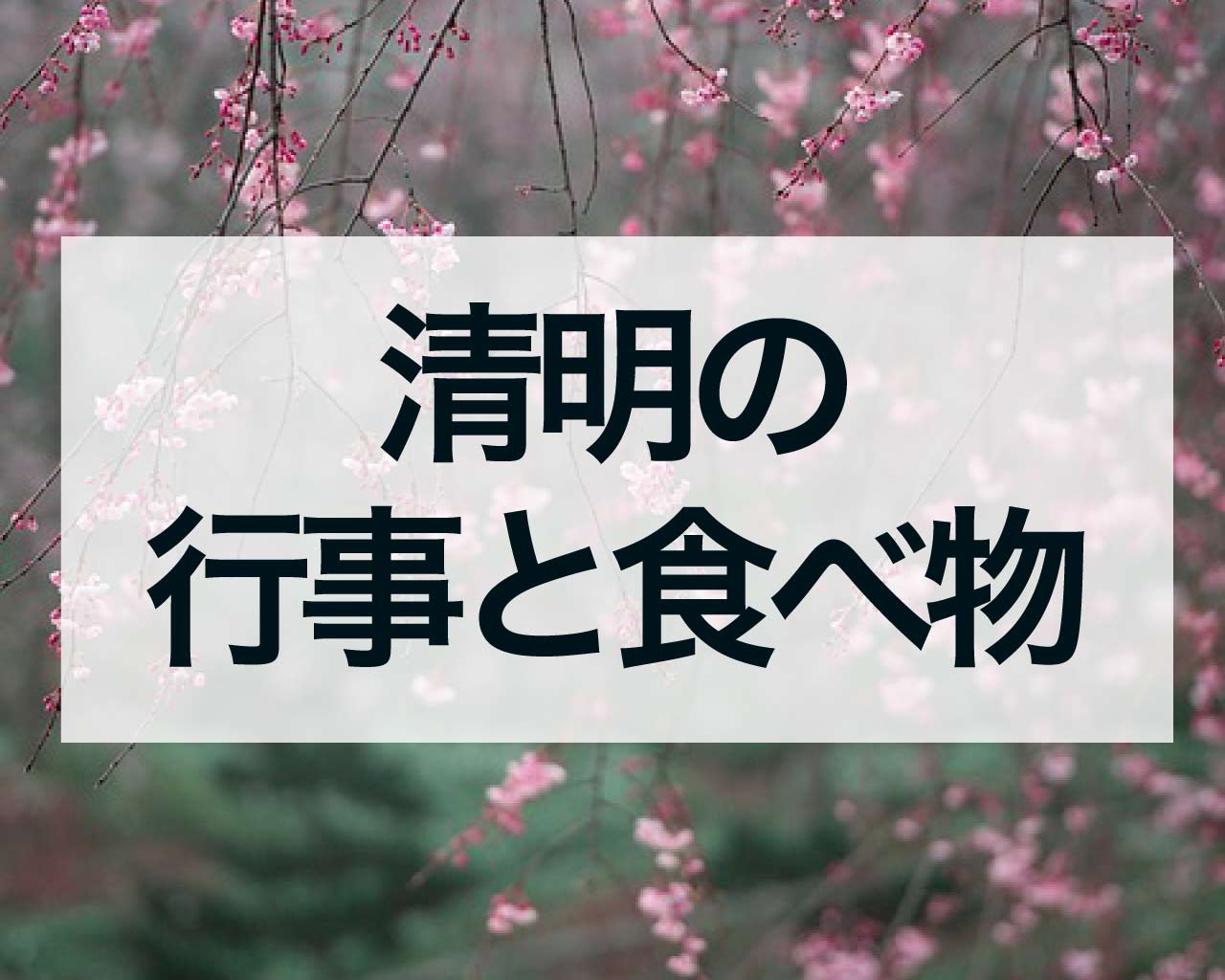



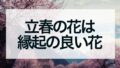

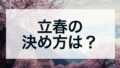
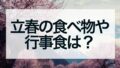
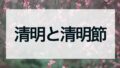



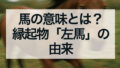
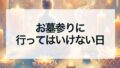

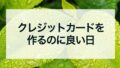
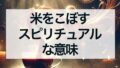
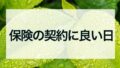
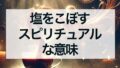
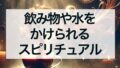
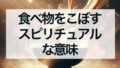
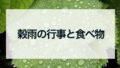
コメント